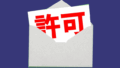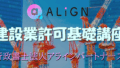静岡の行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務おけるご質問などの経験に基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識を信頼性が高く権威のある静岡県の手引きを基に、アラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを入れて、わかりやすく解説します。
建設業許可の申請をするにあたって基礎となるのが建設業の定義です。この基本を知っていないと、むずかしい建設業許可申請もうまくいきません。建設業法第2条を中心にして建設工事・建設業者・元請・下請など、申請実務の前提となる定義や概念を詳しく解説します。
お願い!:恐れ入りますが、お問い合わせについては、静岡県の方で建設業許可に関する内容でお願い致します。
建設業法
建設業法(昭和24年法律第100号 商法)は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の適正な施工および発注者の保護を目的として制定された法律です。これが第1条に書かれています。
建設業は社会資本整備の根幹を担う産業であり、技術力、経営力の確保や、下請取引の適正化、公共性の高い工事における信頼性確保が求められますので、建設業法によって許可制度や指導監督制度が整備されています。
このようにもっともらしいことが書かれていますが、これを理解していないとなかなか申請がうまくいきませんので、詳しく説明しておきます。
建設業法からの引用です。
(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建設に関する工事で別表の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部または一部について、締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

建設業法第2条
建設業法第2条は、建設業を理解するための「基本定義条文」です。建設業許可申請の可否を判断する場合、建設工事に該当するか?、請負形態で行われているか?、業(仕事)として行っているか?などをこの条文からしっかり確認する必要があります。条文にしたがって詳しくわかりやすく解説します。
建設業法第2条は、建設業に関する基本的な用語を定義しています。「建設工事」や「建設業」、「元請負人」や「下請負人」といった、法の運用に不可欠な概念を明確にする条文です。
- 建設業法第2条の条文を要約すると、次のような構成になっています。
- 「建設工事」とは、土木・建築その他の工作物の建設・改造・修繕等に関する工事であること
- 「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う業種であること
- 「建設業者」とは、建設業を営む者であること
- 「発注者」「元請負人」「下請負人」などの定義
この条文は、建設業許可の対象範囲を判断する場合の基本となるので正確な理解が欠かせません。必ずしっかり理解しておきたいものです。
建設工事とは
建設業法第2条第1項では、「建設工事」を次のように定義しています。
「土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、解体又は除去をいう。」
「建設工事」とは単に建物を新築することだけでなく、改修・修繕・解体なども含まれます。また、道路、橋梁、河川工事などの土木工事も含まれ、建設業法施行令第1条で具体的に29業種に分類されています(たとえば、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業など)。
建設業許可の業種区分・29業種一覧
建設業法でいう29業種とは、2つの一式工事と27の専門工事で成り立っています。
一式工事
土木一式工事と建築一式工事の2業種です。
土木一式工事は総合的な企画、指導、調整のもとにダム、道路、橋梁などの土木工作物を建設、補修、改造する工事全般を指します。複数の専門工事を組み合わせた大規模で複雑な工事なので一式となっています。
建築一式工事も同じく、総合的な企画、指導、調整のもとで建築物を建設する工事のことで、複数の専門工事をまとめて管理・施工する大規模な工事を指しており、一式となっています。
専門工事
専門工事は、次の27業種になります。
・大工工事業・左官工事業・とび土工工事業・石工事業・屋根工事業
・電気工事業・管工事業・タイルれんがブロック工事業・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業・舗装工事業・しゅんせつ工事業・板金工事業・ガラス工事業
・塗装工業・防水工事業・内装仕上工事業・機械器具設置工事業
・熱絶縁工事業・電気通信事業・造園工事業・さく井工事業・建具工事業
・水道施設工事業・消防施設工事業・清掃施設工事業・解体工事業
あまり馴染みのない業種を解説しておきます。
・とび・土工工事業は、建設工事の基礎となる、足場の組み立てや鉄骨の組み立て、土砂の掘削、盛上げ、コンクリートの打ち込みといった、準備的または基礎的な工事全般を指しています。
・しゅんせつ工事とは、河川や港湾、運河などの水底を浚って土砂やヘドロを取り除く土木工事のことです。
・さく井工事業とは、さく井機械等を用いて地下に穴を開ける掘削工事や、井戸の設置、揚水設備の設置などを行う事業のことです。温泉、石油、天然ガスなどの掘削などです。
・建具工事業とは、木製や金属製のドア、窓、障子、襖、シャッター、自動ドアなどの建具を工作物に取り付ける工事を行う事業です。

建設業とは
第2条第2項において、「建設業」とは「建設工事の完成を請け負う営業」とされています。
ここで重要なのは「請負」と「営業」という2つの言葉です。
請負とは、他人の注文に応じて工事を完成させる契約関係を指します。単なる労務提供(派遣や日雇い)とは異なり、結果としての「完成責任」を負う点が特徴です。
営業とは、反復継続して行う意思をもって行う事業活動を意味します。したがって、1回限りの個人的な手伝いなどは建設業に該当しません。
この定義によって個人事業者であっても請負形式で建設工事を反復継続して行う場合は「建設業者」となり、許可が必要になります。この定義から個人事業主であっても建設業許可の対象になるという根拠が出てきます。
建設業者と建設業を営む者とは
「建設業者」とは、第2条第3項において「建設業を営む者をいう」とされています。ここでの「営む」とは、反復継続して建設工事の請負を行う意思をもって事業として行うことを意味します。
法人・個人を問わず、建設工事の請負を業として行う者はすべて「建設業者」に該当し、一定規模以上の工事を請け負うためには建設業許可が必要です(第3条)。
ここで重要なのは、「建設業を営む者」とは許可を受けている、許可を受けていないを問わず、すべての建設業を営む者をいいます。下記にわかりやすくまとめておきます。
- 「建設業を営む者」とは次の3つを指しています。
- 建設業者(建設業許可を受けた者)
- 無許可業者(許可を受けなければならないのに建設業許可を受けていない)
- 軽微な建設工事のみを請け負う者(建設業許可は不要)
このように、官公庁の文章は建設業者と建設業を営む者は異なっていますので注意が必要です。
下請契約とは
建設業法第2条第4項において、「下請契約」とは「建設工事に関し、元請負人と下請負人との間で締結される請負契約」と定義されています。
つまり、発注者から直接請け負った者(元請)が、さらに他の者に工事の一部を請け負わせる関係のことを指しています。
なお、一次下請・二次下請と階層が深くなる場合もあり、法は元請のみならず下請間の関係にも監督が及ぶ仕組みになっています。
発注者とは
建設業法第2条第5項において定義されており、「発注者」とは、建設工事を注文する側、すなわち「工事を発注し、完成物の引渡しを受ける者」を指します。
一般的には施主や元請の顧客であり、公共工事では国・地方公共団体、民間工事では企業や個人が該当します。
発注者は建設業許可は必要ありませんが、建設業法の趣旨上、工事の契約内容や下請関係の適正化を図るために重要な立場にあります。
元請負人とは
「元請負人」とは、発注者から直接建設工事を請け負う者です。
元請は、下請業者に対する指導・監督責任を負い、下請契約の内容や支払条件などに関しても建設業法の規制が及びます(例:第19条の3「下請代金の支払」)。
公共工事では、元請業者が「主任技術者・監理技術者」を配置し、品質・安全管理を行うことが義務付けられています。
下請負人とは
「下請負人」とは、元請負人から請け負った建設工事の全部または一部を請け負う者を指します。
下請負人も、原則として建設業の許可が必要です(建設業法第3条)。また、下請業者は自らさらに他の業者に再下請を出すことも可能ですが、その際にも法令遵守が求められます。
元請・下請関係は、建設業法の最も重要な構造の一つであり、適正な取引と法令遵守が建設業者の信頼を支えています。
建設工事に該当しないもの
一見すると「工事」に見えても、法的には建設工事に該当しないものがあります。これらは建設業許可の対象外であり、許可がなくても行うことができます。代表的なものを以下に示します。また、これらは、兼業に該当して建設業の完成工事高に含めることができません。
代表的な事例は次のとおりです。
除草、草刈、伐採、樹木の剪定、庭木の管理、造林、除雪、融雪剤散布、測量、設計、地質調査、調査目的のボーリング、保守点検、保守・点検・管理業務等の委託業務、清掃、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃、造船、機械器具製造・修理、道路の維持管理、施肥等の造園管理業務、建設機械の賃貸、リース、建売住宅の販売、社屋の工事、資材の販売、物品販売、機械・資材の運搬、採石、宅地建物取引、コンサルタント、人工出し、解体工事や電気工事で生じた金属等の売却収入、JVの構成員である場合のそのJVからの下請工事等
製造のみを行うもの
建設現場での施工を伴わず、工場等で製造して引き渡すだけのもの(たとえば、鉄骨・サッシ・プレハブの製造)は「物品の売買」に該当し、建設工事ではありません。
ただし、現場での組立や設置を伴う場合は建設工事とみなされることがあります。
労務の提供のみ
単に作業員を派遣したり、労務を提供するだけの場合(たとえば、人夫出し、作業員の派遣)は請負契約ではなく、労務供給契約となるため建設業には該当しません。
建設業は「完成責任を伴う請負」であることが前提です。
維持管理や清掃、点検のみ
建物や施設の維持管理・清掃・点検などの業務は、「工作物の建設・改造・修繕」には当たらないため建設工事に含まれません。(例)設備の定期点検、清掃、除草、雪下ろし、道路の巡回パトロールなど。
設計や調査のみ
建設コンサルタントや設計事務所による「設計」「測量」「調査」は、施工を伴わないため建設工事ではありません。ただし、これらに基づく施工を行う場合は建設業許可が必要になります。
家具・備品の搬入や設置
什器やオフィス家具の搬入、機器の設置のみを行う場合(施工を伴わないもの)は建設工事に該当しません。一方で、床や壁への固定、配線・配管工事などを伴う場合は建設工事に含まれることがあります。
最後に
国土交通省や静岡県の文章は、平易な言葉であっても、このように一般的な理解では意味が異なる場合がありますので注意が必要です。
いずれにしても、建設業許可は、煩雑で手間のかかる許認可制度です。静岡の行政書士法人アラインパートナーズでは、経験豊富で行政に詳しい公務員出身の行政書士がご担当させていただきますので、安心して任せることができます。ぜひ、ご相談ください。静岡県内のご相談であれば、遠慮なくご相談ください。