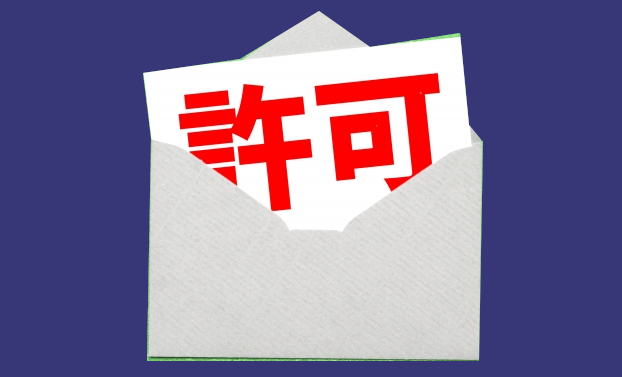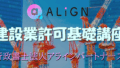国土交通省によれば、令和7年2月1日より、建設業法改正によって特定建設業許可等の金額要件が上がっています。近年の建設工事費の高騰を踏まえて、特定建設業許可をはじめとする各種の金額要件について見直したとのことですので詳しく解説します。
(参照元)令和6年12月 改正建設業法について
国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001855436.pdf
お願い!:恐れ入りますが、お問い合わせについては、静岡県の方で建設業許可に関する内容でお願い致します。
建設業法とは
建設業法は、建設工事の適正な施工と建設業者の健全な経営を目的とする法律です。具体的には、建設業者の営業・許可制度、下請取引の適正化、施工管理体制の整備、入札参加資格要件の基準などを規定しています。
建設業における契約関係や下請管理、施工体制台帳の作成義務などが建設現場の安全と発注者保護に直結するため、法律・施行令・通達レベルで細かく規制されています。
建設業法 第一章 総則の引用です。
(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

建設業許可とは
建設業を営む場合、原則としてこの法律に基づく国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可が必要です。
建設工事の依頼を請け負う営業するためには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかに関わらず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいとされています。
国土交通省のホームページからの引用です。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
「木造」建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
「住宅」住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2]建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
一般建設業許可とは
一般建設業許可は、「元請として下請けに出す金額(下請代金)が比較的小規模な工事」を行う場合に必要な許可になります。
一般許可を受けていれば、下請に対して比較的小額の工事を発注したり、または元請として工事を請け負ったりできますが、大規模な下請発注(一定の金額以上)を行う場合には一般許可だけでは足りずに特定建設業許可が必要になります。
一般許可の取得要件は、経営業務の管理責任者の在職実績、営業所技術者(旧専任技術者の配置、財産的基礎などを満たすことです。
経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業の許可を取得するために必要な、営業取引上の対外的な責任を負い、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する経験を持つ責任者のことです。営業所に常勤している必要があります。
営業所技術者とは、建設業許可を得るために、建設業の営業所ごとに常勤で設置が義務付けられている技術者のことです。請負契約の適正な締結や工事の適正な履行を技術面から支える役割を持ち、一定の資格や経験が求められます。

特定建設業許可とは
特定建設業許可は、元請業者が下請けに出す工事金額が大きい場合に求められる上位の許可になります。
特定建設業者には、監理技術者の配置義務、下請代金の適正な管理、施工体制台帳の作成や整備など、より厳格な施工管理と下請管理義務が課されます。これにより、大規模工事における品質・安全・下請企業の保護が図られています。
特定建設業許可の要件
特定建設業許可を受けるための主要な要件は次のとおりです。
金額要件
金額が改正されて、発注者から直接(元請負人として)請け負った工事について、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は特定建設業許可が必要になります。
技術的要件
監理技術者の設置など、現場ごとの技術管理体制を整備することになります。
財産的要件
財産や資金繰りが一定水準を満たすこと。許可種別や業種ごとに要件があります。
誠実性要件
欠格事由に該当しないこと(暴力団関係、重大な法令違反など)。
その他
施工体制台帳の作成・保存義務や下請契約の適正化等、下請保護に関する義務が強化されています。
施工体制台帳とは、特定の建設工事において、元請業者が下請業者を含め、工事に関わるすべての建設業者の情報、施工範囲、技術者名などをまとめた書類です。建設業法によって作成が義務付けられており、工事の品質・工程・安全を確保し、トラブル防止や法令違反を防ぐことを目的としています。
令和7年建設業法改正の主な内容
令和6年(2024年)末に閣議決定された政令改正等により、建設業に関する複数の規定が見直され、令和7年(西暦2025年)にかけて段階的に施行されています。
主な目的は物価・資材・人件費の高騰を踏まえた要件の見直しと、労務費の適正化・下請保護の強化などです。
- 令和7年建設業法改正のポイントは次の通りです。
- 金額要件の引上げで特定建設業許可等の要件や、施工体制台帳等の作成が必要となる金額基準の引上げ。
- 監理技術者・専任技術者等の要件の合理化(ICT活用など)、専任の取り扱い、業務の現代化に合わせた柔軟化および明確化など。
- 労務費や下請取引の適正化に資する規定強化、労務費の基準、原価割れ契約・低い労務費の排除に向けた措置の検討・導入など。
- 工期に関する基準の策定、建設工事の適正な工期設定を促すため、国土交通大臣が標準的な工期の設定の考え方を定めることになります。
- 独占禁止法との連携強化、不当に短い工期による契約や、一方的な下請代金の減額など、不適切な取引に対する規制が強化されます。
特定建設業許可の金額要件の見直し
令和7年の改正で注目されたのが金額要件の引上げです。特定建設業許可の金額要件は、長期間据え置かれていましたが、経済情勢の変化や物価・賃金の上昇により、現行の4,500万円(建築一式は5,000万円)という基準が、現在の建設業界の実態と乖離しているとの指摘があり、改正されることになりました。
国土交通省の政令改正説明資料によれば、代表的な改定内容は次のとおりです。
特定建設業許可を要する下請代金の下限
・改正前:4,500万円(建築一式工事は7,000万円)
・改正後:5,000万円(建築一式工事は8,000万円)
上記以上となる場合、特定建設業許可が必要になります。
施工体制台帳等の作成を要する下請代金の下限
・改正前:4,500万円(建築一式工事は7,000万円)
・改正後:5,000万円(建築一式工事は8,000万円)
施工体制台帳の作成義務や、現場における監理技術者配置などの運用面で影響します。
その他の金額基準
特定専門工事の対象となる下請代金の上限等、細則的な見直し項目も含まれているため、業種別の取扱い(電気工事、管工事など)にも影響する場合があります。
建設企業への影響
元請で一件あたりの下請代金が増える見込みのある企業は、これまで一般建設業許可で対応していた案件が特定建設業許可の対象になる可能性があります。
元請としての請負契約の見積り・発注設計を見直し、下請代金の区分によって必要となる許可や現場管理体制(監理技術者配置、施工体制台帳作成)を事前に検討する必要があります。
今後の注意点
今後は契約書と見積りの確認したほうがよいでしょう。下請に出す予定の金額が新基準でどう扱われるかを見積り段階で確認して、許可要否を判定しておきます。
建設業許可の早期取得検討する。今後、同種の大口案件を受注する可能性がある場合は、早めに特定建設業許可の取得を検討しておくようにします。
監理技術者などの配置、特定に該当する案件については監理技術者の確保や、施工体制台帳の整備体制をあらかじめ構築しておきます。
下請保護措置の遵守も重要になります。下請代金の支払条件、適正価格の確保、原価割れ契約のリスク等に注意が必要になります。改正は「低廉な労務費等の排除」にも重点が置かれているため、元請として適正な発注を行う責務が強まります。