建設業では、一人で職人として働く「一人親方」という働き方がありますが、最近「偽装一人親方」という言葉がネット検索などで出てきて、社会問題となってきています。
この偽装一人親方とは、実質的には、会社の指揮監督下で労働者として働いているにもかかわらず、形式上だけ、個人事業主、すなわち一人親方として扱われている場合、そのような働き方のことです。
「偽装一人親方」とは何なのか、また、その法的な問題点や建設業法との関係について詳しく解説します。
お願い!:恐れ入りますが、お問い合わせについては、静岡県の方で建設業許可に関する内容でお願い致します。
偽装一人親方とは
「一人親方」は、会社などの法人に属さずに、個人事業主として現場で働く職人さんのことです。元請や下請業者と「請負契約」を結んで、現場などの仕事を請け負う形で、労働者ではないとされているために、労災保険などの制度も「労働者」とは異なっています。
「偽装一人親方」とは、実態としては会社などの雇用関係のある労働者であるにもかかわらず、形式上だけ、請負契約を結んで、あたかも一人親方であるかのように装って働かせる事例のことです。実態と法律上の形式が異なっている状態にあります。
実態として、勤務時間や作業内容が元請の指揮命令に従っていて、資材や仕事道具なども支給されているようであれば、実質的には(社員としての)「労働者」と判断される可能性が高いと思われるケースです。
- 具体的には、次のような場合に「偽装一人親方」と該当する可能性があります。
- 特定の建設会社から(長期間)継続的に仕事を受けている場合
- 仕事のすすめ方や時間管理について、建設会社の指示を受けている場合
- 建設会社の所有する機材や道具、支給の材料などを使用している場合
- 報酬などが、決まった給料ではなく時間や作業量に応じて支払われている場合
- 請負契約のような結果である成果物に対する対価ではない場合
- ほかの建設会社の仕事をすることがほとんどない場合
すなわち、会社員と見せかけていて、実態は個人事業主、親方として働いている場合です。
このような状況で働かされており、労働者としての保護を受けられないのに、実質的に、会社所属の労働者と同じような働き方をさせられているという点が社会問題となっています。
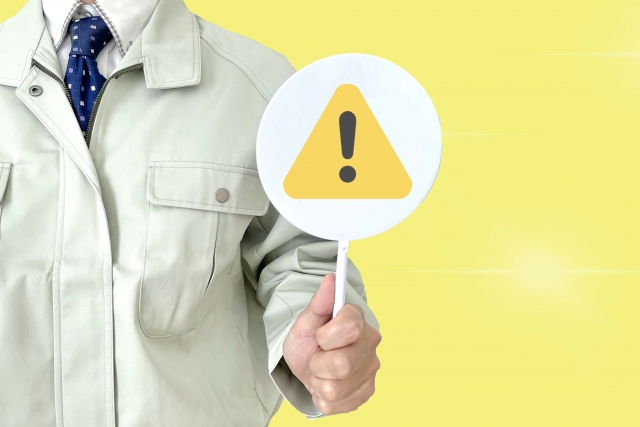
なぜ偽装するのか?
建設会社などの事業者が偽装一人親方を利用する理由としては、社会保険料や労災保険料(労働保険料)の負担をしないようにするためと言われています。
労働者として雇用する場合であれば、事業者には、当然、労働保険や社会保険への加入義務、労働時間、休憩、休日などの労働基準法の遵守、最低賃金の保証、労働災害時の対応や保護、予防が必要になります。
ところが、請負契約であれば、このような義務を免れることができるため、これらの諸費用のコスト削減や法的な責任の回避の方法として悪用されることになります。
また、労働者がこのような状態を受け入れてしまう背景には、仕事を得るための選択肢がない場合、ほかの働き口が見つからずに、やむを得ず偽装一人親方として働くことを選択せざるを得ない場合とか一時的な収入の確保のために目先の収入を優先して、将来的な保障や権利について十分に理解していない場合、労働法制度の理解不足もあるでしょう。 労働者としての保護されるべき立場であることを認識していないことがあると思われ、これが社会問題となっています。

一人親方は建設業許可が必要か?
また、一人親方として扱われると建設業許可の取得という負担も負わされる可能性もあります。
一人親方が請け負う工事の金額や内容によっては、建設業許可が必要になる場合があります。
元請として工事を請け負う場合ですが、具体的には次のような基準があります。
500万円(税込)以上(建築一式工事は1500万円以上)の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になります。簡単に取得できる許可ではありません。煩雑な書類の提出や資格、経験年数が必要になることがあります。
一人親方であっても一定規模以上の工事を請け負う場合は、法人・個人問わず建設業許可を取得しなければならなくなります。
建設業法上は「請負契約」であることが前提とされていますが、実態が労働契約に近いと判断された場合、契約の形式を問わず、建設業法違反となる可能性もあります。
偽装一人親方として働いている人が、実際には建設業許可が必要な規模の工事を無許可で請け負っている場合は、建設業法第3条に違反する無許可営業となる可能性があります。
建設業許可とは
建設業許可とは、営業で建設工事を請け負うために必要になっている国や都道府県の許可のことです。
建設業法に基づいており、一定の規模や内容の工事をする場合には、この許可を取得しなければなりません。
許可は29業種に分類されていて、それぞれの業種ごとに取得することになっています。
経営業務の管理責任者や専任技術者の設置、財務的要件、誠実性要件などの条件を満たす必要があります。
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。それぞれは、許可を受ける時に必要な要件や、許可を受けた後にできる工事が違ってきます。
偽装一人親方は建設業法で違反になるのか?
偽装一人親方の状態とされた場合は、建設業法や労働関係法令に違反する可能性があります。
違反となる主な法令
建設業法
請負契約に見せかけた実態労働契約は、建設業法第19条(不正の手段による許可取得など)に抵触する可能性があります。
建設業許可を受けている建設業者が、実質的に労働者にもかかわらず、労働者を個人事業主として扱って、社会保険などに加入させない場合は、建設業者の社会保険加入義務(建設業法第27条の23)を怠っているとみなされる可能性があります。建設業者は、原則として健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入しなければなりません。
労働基準法・労働契約法
実態が労働者であるにも関わらず、雇用契約を結ばずに請負契約とするということは、違法な労働形態と見なされることがあります。
労働者として扱われるべき労働者を個人事業主として扱うことは、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法令に違反する可能性もありますが、この法令違反は建設業法に基づく監督処分の対象となることもあります(建設業法第28条)
労災保険法
労働者としての労災補償がなされていないことは、会社側が行政処分や損害賠償請求を受けることがあります。
下請代金支払遅延等防止法
建設業者が、下請契約ではなく請負契約の形式を悪用して、下請代金の支払いを不当に遅延させたり、不当に低い金額で契約したりする場合は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)に違反する可能性があります。
行政指導や指摘の可能性
建設現場での労災事故などがあって、偽装一人親方がわかってしまうケースがあります。その場合、最悪、労働基準監督署からの是正勧告、元請会社に対する行政指導、公共工事の入札停止措置などの厳しい処分を受けることがあります。
直接「偽装一人親方」という行為が建設業法に明記されていないので、違反となるわけではありませんが、偽装一人親方の状態であれば、建設業法やその他の関連法規に抵触する可能性が十分にありますので注意が必要です。
まとめ
偽装一人親方は、建設業法に直接的な違反規定があるわけではありませんが、社会保険加入義務違反、無許可営業、下請法違反、労働関係法令違反など、多くの法令に抵触する可能性があります。かなり危ない状態であると言えます。
偽装一人親方は形式上では「請負契約」としていたとしても、実態としては労働者であれば、法的に問題のある行為となってしまいます。
建設業法をはじめ、労働関連法令や保険制度との関係を正しく理解して、適正な契約形態とすることが、企業と職人(労働者)の両方のリスクの回避となります。
一人親方としての営業活動を検討している方や、現場での職人などの人材管理に不安を感じている会社の方は、静岡の行政書士でアラインパートナーズにご相談ください。





