建設業許可を取らずに建設業を営んだり、許可の要件を満たさなくなったにも関わらず事業を継続したりすると、法律によって罰金や罰則が科せられることがあります。建設業なしで500万円以上の契約をした場合、1回だけなら大丈夫?・・・発覚しても文書指示だけで済む?・・・・気になるところを詳しく解説します。
お願い!:恐れ入りますが、お問い合わせについては、静岡県の方で建設業許可に関する内容でお願い致します。
建設業許可とは
建設業許可は、一定の規模や請負金額以上の建設工事を請け負う事業者が取得しなければならない許可です。
建設業法に基づいて適正な経営能力や財務基盤、技術的要件を満たしていることを証明します。
一定規模や請負金額以上の建設工事を請け負う際に、建設業法に基づいて国土交通大臣または都道府県知事から取得しなければならない許可です。
建設業者の資質を確保して建設工事の適正な施工と発注者の保護を図ることを目的としています。
- 建設業許可が必要となるのは、次の条件に該当する場合です。
- 1件の工事の請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1500万円)以上の場合
- 許可が必要な業種(建築、大工、電気、管工事など29業種)に該当する工事を請け負う場合
許可を取得すれば発注者や元請業者からの信頼が得られるだけでなく、公共工事の受注ができるようになります。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
軽微な建設工事とは
・建築一式工事では、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
「木造」建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
「住宅」住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
・建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
建設業許可の種類
- 建設業許可には次の2種類があります。
- (大臣許可)複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合
- (知事許可)一つの都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合
また、許可を受ける業種は、工事の種類に応じて29種類に分かれています。

建設業許可違反の事例
代表的な建設業許可違反には次のような事例があります。
(無許可営業)許可を受けずに500万円以上の工事を請け負う
(名義貸し)他人の建設業許可を借りて工事を請け負う
(不正入札)談合や贈収賄を伴う入札行為
(虚偽申請)建設業許可申請時に虚偽の財務情報や技術者情報を提出、許可申請時や更新時に、事実と異なる内容を記載して提出した
(営業停止処分無視)行政処分に従わず営業を続ける
(許可要件の不保持)許可取得後に、経営業務の管理責任者や専任技術者などの許可要件を満たさなくなったにも関わらず、事業を継続した
(変更届の不提出)許可を受けた内容に変更があった場合(例:代表者の変更、営業所の移転など)に、定められた期間内に変更届を提出しなかった
(標識の不掲示)建設業の許可を受けていることを示す標識を、営業所や建設工事の現場に掲示しなかった
このような違反は処罰の対象となります。
経営業務の管理責任者とは、建設業の営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務を総合的に管理・執行する経験を有する者です。
専任技術者とは、建設業の営業所に常勤して、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保する人のことです。
建設業許可違反の罰金と罰則
建設業許可違反を行った場合は、建設業法に基づいて、次の罰則が科されることがあります。
(無許可営業)3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)
(名義貸し)1年以下の懲役または100万円以下の罰金(建設業法第47条の3)
(虚偽申請)6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金(建設業法第50条)
(変更届の不提出)50万円以下の罰金
(不正な入札行為)独占禁止法違反として課徴金の対象となることもある
(標識の不掲示)10万円以下の過料
これらの罰則は、違反行為を行った事業者本人だけでなく、法人の場合は代表者や役員なども処罰の対象となる可能性があります。
過料(かりょう)とは、行政法規上の義務違反に対して、国や地方公共団体が金銭を徴収する制裁です。刑罰ではないため、前科にはなりません。
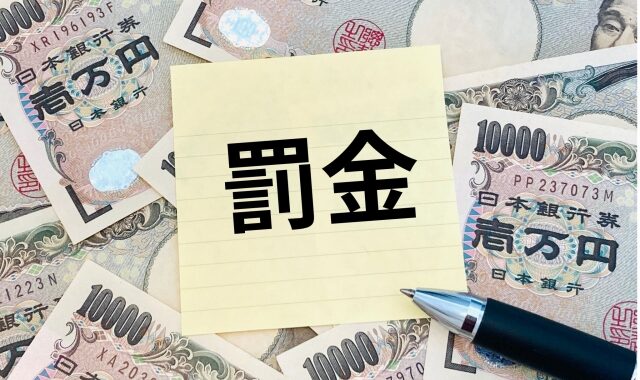
行政処分と刑事処分
建設業許可違反には、行政処分と刑事処分の両方が適用される場合があります。
行政処分
行政処分は、国土交通省や都道府県知事が行うもので、次のようなものがあります。
(指示処分)違反内容の是正を求める
(営業停止処分)一定期間、営業を停止させる
(許可取消処分)悪質な場合、建設業許可を取り消す
行政処分とは、行政機関が法令に基づいて、国民に権利を与えたり義務を負わせたりする行為です。罰則や制裁を課す命令で、法的強制力があります。
刑事処分
刑事処分は、警察や検察が違法行為を摘発して裁判所で刑罰を科すものです。
(懲役刑)最長3年の懲役が科される場合もある
(罰金刑)最高300万円の罰金
(執行猶予付き判決)初犯の場合、執行猶予が付くこともある
指示処分と営業停止処分の違い
指示処分は「警告・是正指示」、営業停止処分は「営業禁止」という違いがあります。
指示処分は、建設業者が建設業法や関連法令に違反した場合、または建設工事の施工や安全管理などに不適切な点が見られた場合に、国土交通大臣または都道府県知事が行う行政処分の一つです。
指示処分
違反が軽微な場合に適用される。
事業者に対し、違反を是正するよう命じる。
営業自体は継続可能。
例えば、虚偽の申請があったが軽微な場合など。
指示処分は、違反行為を速やかに是正させ、将来的に同様の違反が発生しないように指導することを主な目的としています。
行政庁は、違反の内容に応じて、具体的な改善策や是正措置を建設業者に指示します。
- 改善策や是正措置の指示は、たとえば次のような内容です。
- 施工方法の改善
- 安全管理体制の見直し
- 下請業者との契約内容の改善
- 帳簿書類の作成・保管方法の改善
- 従業員への指導・研修の実施
指示処分は、一般的に、営業停止処分や許可取消処分ほど重大ではない軽微な違反に対して行われることが多いですが、同じような違反を繰り返した場合は、より重い処分になる場合もあります。
指示処分を受けた場合でも、建設業者は通常通り業務を継続することができます。
営業停止処分
営業停止処分は、違反が重大または再犯の場合に適用されます。一定期間、営業を停止させられることになってしまいます。
例えば、無許可営業や名義貸しなどの悪質な違反です。営業ができなくなるため、事業への影響が極めて大きくなります。
営業停止処分は、建設業者が建設業法や関連法令に重大な違反を犯した場合、または建設工事において重大な事故や不誠実な行為があった場合に、国土交通大臣または都道府県知事が行う行政処分です。
営業停止処分は、建設業者による悪質な違反行為に対して、一定期間業務を停止させることで制裁を加えることを主な目的としています。
重大な違反行為を行った建設業者を一時的に排除することで、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護する狙いもあります。
営業停止処分を受けた建設業者は、定められた期間(数日から数ヶ月程度)、新たな建設工事の請負契約を締結したり、建設業としての営業活動を行うことが禁止されます。
ただし、処分前に契約した工事については、継続して施工することが認められる場合があります。
営業停止処分は、無許可営業、名義貸し、重大な手抜き工事、安全管理の著しい怠慢による重大事故の発生など、社会的な影響も大きい、より重大な違反に対して行われます。
違反にならないようにする対策
建設業許可違反を防ぐためには、次のような対策が必要です。
許可の有無を確認
許可が必要な工事を請け負う場合は、事前に確認し、許可取得を行うようにします。請け負う工事が建設業許可を必要とする規模かどうかを常に確認します。判断に迷う場合は、行政書士などに相談することをおすすめします。もちろん静岡の行政書士法人のアラインパートナーズでも受け付けております。
許可要件の維持
許可取得後も経営業務の管理責任者や専任技術者などの要件を満たし続けるようします。退職した場合などは、速やかに後任者を選任する必要があります。
変更届の提出
会社名、代表者、所在地、営業所など、許可内容に変更があった場合は、定められた期間内に必ず変更届を提出します。
名義貸しは止める
建設業許可を持っていない業者と不正な取引をしない。
標識の掲示
営業所や建設工事の現場には、建設業許可を受けていることを示す標識を適切に掲示します。
正しく申請や書類の提出をする
財務状況や技術者情報など、虚偽の申請をしない。
建設業許可違反は存続に関わる重大な問題となります。許可を取得して法令を遵守するようにしましょう。わからないことがあれば、静岡の行政書士法人のアラインパートナーズにお問い合わせください。






