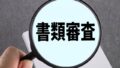公共工事に参加するには経営事項審査(経審)を受けなければなりません。
経営事項審査は公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模や経営状況などの客観事項を数値化した、建設業法に規定されている審査です。略して経審(けいしん)とも呼ばれています。
経審がいつから始まったのか、すべての公共工事で必要なのか、大企業に有利ではないのか、赤字企業は参加できないのかなど、公共入札と経営事項審査に関する両者の関係などを詳しく解説します。
お願い!:恐れ入りますが、お問い合わせについては、静岡県の方で建設業許可に関する内容でお願い致します。
経営事項審査はいつから公共工事で必要になったのか?
経営事項審査(経審)は、1950年に経営事項審査の前身ともいうべき「工事施工能力審査」が、主要発注機関によって行われました。その後、1973年に名称を「経営事項審査」に改められて現在に至っています。
建設業法 第27条の23では第1項では「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」と規定されており、第2項では経営事項審査は、「経営状況」及び「経営規模等」(経営規模、技術的能力、その他の客観的事項)について数値による評価をすることにより行う」と規定されています。
公共投資の拡大に伴って、工事施工能力のない業者をなくして(排除して)、工事の品質や安全を守る目的で制度化されました。今でも公共工事の入札に参加するための必須要件となっています。

公共入札に参加するには経営事項審査は必須か?
公共入札に参加するには経営事項審査が必須です。
建設業許可だけでは入札できず、経審を受けて審査結果通知書を持っていることが公共工事入札の前提条件です。
経審結果通知書(経営事項審査結果通知書・総合評定値通知書)には、経営規模、技術力、社会性、経営状況といった会社の状況を数値化した「総合評定値(P点)」が記載されており、この点数が高いほど大規模な公共工事の入札に参加する資格が得られます。
まず、建設業許可を取得して、経営事項審査を受審してから入札参加資格審査となり名簿登載となます。この経審の手続きを経ないと公共工事に関わることはできません。
入札参加資格審査では、事業者は必要な書類を提出して審査を受け、その企業が公共工事の相手方としてふさわしいかどうか、実績や技術力、経営状況などが判断されることになります。
小規模工事でも経営事項審査は必要なのか?
結論として、小さな工事であっても経審は必要です。
たとえ100万円程度の小さな工事でも公共発注であれば経審を受けていないと入札できません。
ただし、例外的に「少額随意契約」の場合、発注者が経審を条件としないケースもあります。とはいえ、通常の入札では規模にかかわらず経審が必須です。
入札の少額随意契約(少額随契)とは、公共機関が契約金額が一定額以下(少額)である場合に、競争入札を省略して、複数の事業者から見積もりを徴収して契約相手を決めることができる制度です。

すべての公共工事で経営事項審査は必要?
原則として、すべての公共工事で経審が必要です。
- 経審が不要な例外的なケースは次のとおりです。
- 少額随意契約
- 災害復旧など緊急工事で特例的に経審を省略
ただし、通常の公共入札では必ず経審が前提条件になります。
日本全国の公共入札で経営事項審査は利用されている?
経営事項審査は全国統一の制度です。
国の直轄の工事だけでなく、都道府県や市町村の地方自治体の工事でも共通して経審が必要になっています。
ただし、各自治体ごとに「格付け基準」や「点数の運用」に違いがあるため、同じ点数でもAランクに入れる自治体とBランクにとどまってしまう自治体があるなどの差はあります。
経営事項審査は大企業に有利ではないのか?
経審では売上や資本金が評価されるので 大企業が有利な面はありますが、小規模工事希望制度や、中小企業向けの工事枠があるので中小企業にも配慮がなされています。
また、大企業と中小企業が同じ条件で競うのではなく、規模に応じた工事ランクで競争できる仕組みにもなっています。
経審は規模だけでなく、技術力や経営状態、社会性といった多角的な観点から評価されるために、中小企業でも工夫次第では高い点数を得ることは可能になっています。例えば、技術力や労働環境の改善、無借金経営などが評価を高める要因となっています。
赤字だと経営事項審査で入札できないのか?
赤字だからといって入札できないわけではありませんが、経営事項審査では「経営状況分析(Y評点)」が重視されており、赤字決算が続くと点数が下がり、入札参加資格に必要な基準点に届かなくなる恐れがあります。
基本期には黒字経営を維持して安定した財務基盤を示すことが、入札参加を継続するための条件になります。
Q&A
Q. 経営事項審査はいつから公共工事で必要になったのか?
A. 1950年に「工事施工能力審査」として始まり、1973年に「経営事項審査」と改められました。現在も公共工事入札の必須制度です。
Q. 公共入札に参加するには経営事項審査は必須か?
A. はい、必須です。建設業許可だけでは入札できず、経審を受けて総合評定値通知書を持っていることが前提条件です。
Q. 小規模工事でも経営事項審査は必要なのか?
A. 原則必要です。例外として、少額随意契約や緊急工事では経審が省略される場合もあります。
Q. すべての公共工事で経営事項審査は必要?
A. はい、原則必要です。ただし、少額随意契約や災害復旧などの緊急工事では省略されるケースがあります。
Q. 日本全国の公共入札で経営事項審査は利用されている?
A. はい、全国統一制度です。国や地方自治体の工事でも共通して必要ですが、自治体ごとに格付け基準や運用が異なる場合があります。
Q. 経営事項審査は大企業に有利ではないのか?
A. 売上や資本金の面では有利ですが、中小企業向けの工事枠や規模別競争制度があり、技術力や経営改善によって中小企業も高得点を得られます。
Q. 赤字だと経営事項審査で入札できないのか?
A. 赤字でも入札は可能ですが、経営状況分析(Y評点)が下がるため、赤字が続くと基準点を満たせず資格を失う恐れがあります。