静岡県の経営事項審査における合併、事業譲渡、会社分割について詳しく解説します。
なお、情報の確認は、静岡県の経営事項審査の手引きで確認済みです。
経営事項審査とは
経営事項審査とは、公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受ける必要がある審査のことです。
企業の施工能力や財務状況、技術力などを客観的に評価して、その結果を数値化するもので、公共工事の入札に参加するために不可欠なプロセスとなります。
具体的には、「経営規模等評価」と「総合評定値(P点)」の算出が行われて、公共工事を請け負うためのいわゆる「通知表」のような役割を果たします。
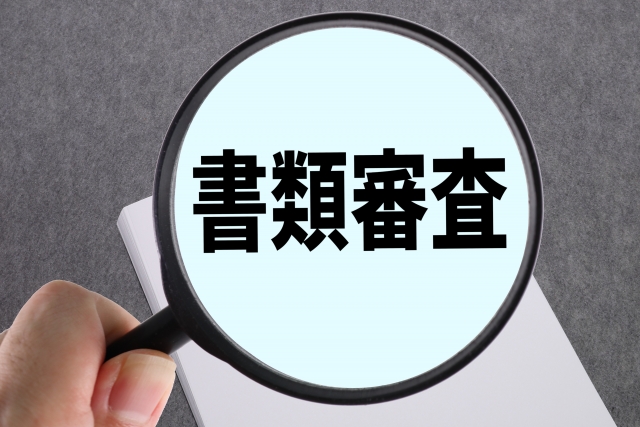
経営事項審査の要件
経営事項審査を受けるには、次の2つの要件を満たす必要があります。
建設業の許可
建設業の許可を受けていることが必須です。経営事項審査を受けるには国や都道府県から建設工事を行うための正式な建設業許可を得ていなければなりません。
経営状況分析
経営状況分析とは、会社の財務状況を客観的に分析することです。具体的には、自己資本額や利益額、キャッシュフローなど、経営の健全性を示す指標を専門機関に提出して分析してもらいます。この分析結果は、経営事項審査の評価項目の一つとなります。
経営事項審査の合併、事業譲渡、会社分割とは
経営事項審査における合併、事業譲渡、会社分割は、それぞれ企業再編の手段であり、建設業許可や経営状況の評価に影響を与える手続きでもあります。
合併は2社が1社になることで、事業譲渡は事業の一部を個別に売買すること、会社分割は事業を包括的に分割して別の会社に引き継ぐことで、いずれも承継会社(引き継ぐ側)の経営事項審査に反映されることがあります。
合併
複数の会社が1社になる再編手法です。
経営事項審査への影響としては、合併後の状況で審査されるのが原則ですが、合併時に経営事項審査を受けることで合併の効果が早期に反映されることになります。
事業譲渡
特定の事業資産を個別に売買する手法であり、従業員の転籍にも個別の同意が必要になります。
経営事項審査への影響としては、会社分割と異なって経営事項審査の項目である「営業年数」は承継されずに、リセットされてゼロになります。
会社分割
会社の事業を複数の独立した法人に分割して、承継会社がその事業の権利義務を包括的に引き継ぐ手法のことです。
経営事項審査への影響としては、分割日時点での事業の実績(完成工事高、技術職員数など)が、分割後の会社に引き継がれて経営事項審査の評点に反映されます。

静岡県の合併、事業譲渡、会社分割について
合併、事業譲渡、会社分割を行った場合は、合併期日等を審査基準日として経営事項審査を受けることができます。
詳細については、事前に静岡県建設業課建設業班へご相談ください。
交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562
(参考通達)
建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(平成20 年3月10 日国総建第309 号)
建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(平成20 年3月10 日国総建第311 号)
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(平成20 年3月10 日国総建第313 号)
経営事項審査の合併、事業譲渡、会社分割の手続き
ポイント
事業承継(合併・事業譲渡・会社分割)を行う場合、建設業許可と経営事項審査(経審)の承継は別々の手続きであり、いずれも事前認可や所管庁との調整が必要です。
なお、空白期間を生じさせないための「事前認可制度(令和2年改正)」が設けられています。
共通の前提と注意点
建設業許可が前提
経営事項審査を受けるためには建設業許可が必要です(承継後の事業体が許可要件を満たす必要があります)。
事前認可(空白回避)
事業譲渡・合併・分割を行う場合、事前に許可行政庁へ認可申請し承認を得ることで、承継日(譲渡日・合併期日・分割期日)に建設業者の地位を移転し、空白期間を避ける制度があります(令和2年改正で制度化)。相続の場合は死亡後30日以内に認可を受ける扱いなどの細則あり。
経営事項審査(完工高・技術者・営業年数 等)の承継
経営事項審査は完工高、技術職員数、営業年数等を評価します。事業承継の類型に応じて「合併時経審」「分割時経審」「承継時経審」等の特例的取扱い(特殊経審)があり、被承継企業の実績等を承継できる場合があります(ただし要件あり)。
合併(吸収合併・新設合併)
ポイント
存続会社(吸収合併)、または新設会社(新設合併)が、承継後に建設業許可の要件を満たすこと。
吸収合併の場合、消滅会社の許可が自動的に存続会社へ移るわけではないため、許可業種の追加や条件の見直しが必要となるケースがある(事前相談が必要)。
経営事項審査上の取扱い
国土交通省の通知に基づき、合併に伴う経営事項審査の承継(合併時経審)が認められる場合がある。承継できる項目(完工高の一部・技術者数等)は、合併の実態や書類で確認され、審査基準日や合併期日などの取扱いが定められています。
手続きの流れ
事前相談(重要)
合併計画が固まったら早めに許可庁(都道府県や地方整備局)へ相談。許可の承継や業種追加の要否を確認。
合併契約書等の準備
合併契約書、株主総会議事録、登記事項証明書、被承継会社の建設業許可関係書類・経審通知書等を準備。
事前認可申請(許可承継)
許可庁へ「許可の承継認可申請」を行う(合併の効力発生日に承継できるよう手配)。承認が出れば空白なしで承継可能。
合併後の経審申請
合併に係る承継を踏まえて、合併後の法人が経審(合併時経審)を申請。被承継会社の完工高明細や技術者の移籍証明等で実体を確認されます。
合併チェックリスト
合併契約書/合併登記の証明(登記事項証明書)
被承継会社の経審通知書(総合評定値・完工高明細)/完工高を裏付ける工事台帳
技術者の職務経歴書・在籍証明・登録台帳(CCUS等)
決算書、納税証明、労働保険・社会保険の加入証明 等。([国土交通省][3])
事業譲渡(営業譲渡・事業譲渡)
要件(ポイント)
譲受人が譲渡を受けた事業について建設業許可要件を満たすこと。
事業譲渡そのものは、譲渡契約の内容と実体(顧客・工事台帳・従業員・技術者の移籍等)で判断され、経審の承継が認められるか決まります。
経審上の取扱い
国交省の通知で譲渡時の経審(承継時経審)の取り扱いが定められており、譲渡対象となった工事実績(完工高)、技術者等を譲受人が承継できるケースがあります。ただし、譲渡の実体(どれだけの業務実体が移るか)を厳格に見られます。
手続きの流れ
事前相談
譲渡契約締結前に許可庁へ相談。空白期間回避のため事前認可を検討。
譲渡契約と証拠の整備
事業譲渡契約書、工事台帳・受注契約書の移転、従業員(技術者)の雇用調整や移籍合意書など。
事前認可申請(必要に応じ)
譲受人が許可要件を満たすか確認したうえで、譲渡日と合わせて許可承継の認可を受ける。
経審申請
譲受人が譲渡を受けたデータ(完工高明細、技術者実績等)を添えて承継を申請。
注意
名義だけの移転は不可です。
実体(工事や技術者、営業拠点等)が移転していることが必要になります。単に契約書上で譲渡しただけでは承継されない可能性があります。
会社分割(吸収分割・新設分割)
ポイント
分割の形態(吸収分割 / 新設分割)により審査基準日や承継のタイミングが異なります。分割承継法人が許可要件を備えていることが必要です。
経審上の取扱い(審査基準日の取扱い)
分割時における経審の審査基準日は、次のように扱われます(国交省通知の要旨)。
吸収分割で分割契約上の「分割期日」があり、その日および当該日に新会社としての実態を備えると認められる場合は分割期日を審査基準日とする。そうでなければ分割登記日を基準にする。
新設分割の場合は原則として設立日(登記日)が基準日になります。ただし、例外あり。
また、分割直前の営業年度終了の日を審査基準日とする「分割直前経審」が既に受けられている場合の取扱い、分割後に分割時経審を分割会社等に申請する必要等、細かい運用ルールが定められています。
手続き
分割計画の確認と事前相談
分割の実行前に許可庁へ分割方式と承継の見込みを相談。
分割契約書・分割計画書等の準備
分割契約書、分割期日の定め、登記事項証明、分割前後の事業実体を示す資料を揃える。
事前認可申請(必要な場合)
分割による許可承継の認可を事前に受け、承継日での空白を回避。
分割時経審の申請
分割後の承継法人が、分割時の審査基準日に基づく経審を申請する。分割前会社は同時に分割直前の経審を提出する等、並行申請が求められる場合があります。
提出書類
合併契約書/事業譲渡契約書/分割契約書・計画書。
合併・分割の登記事項証明書(登記簿謄本)。
被承継会社の経審通知書(総合評定値通知)、完工高の内訳(工事台帳・工事請負契約書等)。
技術者の職務経歴書・在籍証明・就業実績(建設キャリアアップシステムの記録がある場合はそれも)。
承継法人の決算書、貸借対照表、損益計算書、納税証明書。
労働保険・社会保険の加入状況、その他関連する行政手続の証明。
Q&A
まとめを兼ねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。



