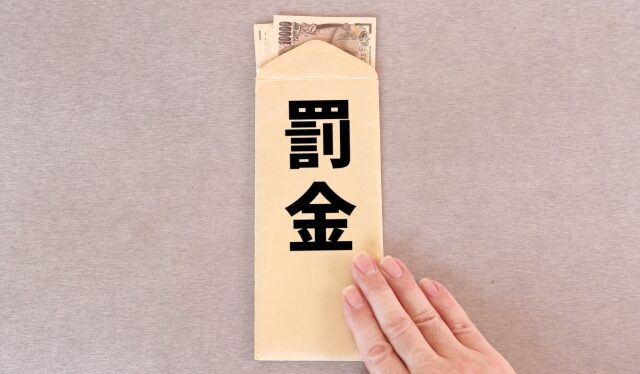2025年の全国版、建設業法と建設業許可関係の違反のニュースとその詳しい解説です。事例の引用先は下記からの抜粋です。
国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/index.html
違反になった場合は厳しい罰則もあります。不安な場合は行政書士法人アラインパートナーズ(静岡県)にご相談ください。
お願い!:恐れ入りますが、お問い合わせについては、静岡県の方で建設業許可に関する内容でお願い致します。
2025年許可取り消し
2025年の建設業許可取り消しの件数は、6件でした。その詳しい内容の代表的な事例について会社名なしで解説します。
事例1
処分の原因となった事実(2件)
・代表取締役である者が令和6年1月26日付けで窃盗、建造物侵入の罪により懲役3年の刑が確定した。このことは、設業法第29条第1項第2号に該当する。
・当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和6年10月12日にその刑が確定した。
処分の内容
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し
解説
建設業法では、一定の犯罪を犯し、刑が確定した者は建設業の許可を維持できないという規定があります。
建設業の経営者には「信用」と「適正な経営能力」が求められています。建設業法第8条には、建設業の許可を受けるための条件(欠格要件)が定められています。
その中に 「禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから一定期間が経過していない者は、建設業の許可を受けられない」 という規定があります。
犯罪で有罪になり、刑が確定すると、「経営者として不適格」と判断され、建設業の許可が取り消されるという規定です。
- 建設業許可の取消しとなると次の影響があります。
- 一定額以上の建設工事を請け負えなくなる
- 他の会社で建設業の経営者になることも制限される可能性がある
- 社会的信用が大きく低下し、取引先や元請業者との契約にも影響が出る
特に、許可を必要とする公共工事や大規模な建設工事には関われなくなるため、経営に大きな打撃を受けることになります。
事例2
処分の原因となった事実
当該建設業者は、令和2年5月21日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類において、事務所及びその机、電話機等の写真を貼付した「営業所概要書」を添付していたが、電話番号は実際には他社の事務所内に設置された電話に係るもので「営業所概要書」等に表示された事務所には固定電話の回線は設置されていなかった。
当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、「経営業務の管理責任者証明書」、「経営業務の管理責任者の略歴書」及び「役員等の一覧表」に常勤の役員ではないA氏を常勤の役員であると記載し、B建築設計事務所に勤務していたにもかわらず「経営業務の管理責任者の略歴書」にその事実を記載せず、同略歴書に記載のある「A事務所」とは建設業の営業に係るものではなく、これらのため、同人は建設業法第7条第1号イの「許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」ではないにもかかわらず、「経営業務の管理責任者証明書」に同人がその経験を有する者であるなどと記載した。
当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、建設業法第7条第2号の「専任のもの」とは営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいい、雇用契約等により当該建設業者と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければならないところ、そのような「専任のもの」ではないC氏を同法第7号第2号に規定する専任の技術者として置いている旨を記載した。
当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者であるA氏が当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、同条第2号の「専任のもの」であるC氏が当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。
当該建設業者は、令和2年許可申請書類(添付書類も含む。)において、1から3までのとおり、虚偽の内容を記載し、令和2年7月17日に、建設業法第3条第1項の建設業の許可を受けた。
処分の内容
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し
解説
虚偽の申請をして建設業の許可を取得していました。この建設業者は、許可を取得するために事実とは異なる情報を申請書に記載していたわけです。
(1)実際には営業所として機能していない場所を「営業所」として申請した。
「営業所概要書」に貼付した写真に机や電話機が写っていたが、その電話番号は他社の事務所のものだった。実態のない営業所である可能性が高い。
建設業法では、営業所は「事業を行う拠点として、適切な設備が整っていること」が求められています。虚偽の営業所申請は違法になります。
(2)経営業務の管理責任者(A氏)の資格要件を満たしていなかった。
「常勤の役員」として申請したが、実際には他の会社(B建築設計事務所)で働いていた
「5年以上の経営経験がある」と申請したが、その経歴には虚偽があった。
申請書に記載した「A事務所」は、実際には建設業とは関係のない事務所であった。
経営業務の管理責任者は「建設業に関する経営経験5年以上」が必要です。虚偽の経歴で許可を得るのは違法となります。
(3)専任技術者(C氏)が、実際には営業所に常駐していなかった。
専任技術者は、営業所に「常勤」して職務に専念することが条件です。
しかし、C氏は実際には営業所に常勤していなかったにもかかわらず、専任技術者として登録されていました。
専任技術者は、適切な技術管理を行うために「営業所に常駐」する必要があります。実際に勤務していないのに専任技術者として登録するのは違法になります。
(4)これらの虚偽情報をもとに、令和2年7月17日に建設業の許可を取得した。
営業所、経営責任者、専任技術者のすべてに虚偽の申請があった。建設業法の許可基準を満たしていなかったにもかかわらず、不正に許可を取得していたことになります。
- 本件に関して、建設業の許可は次の要件が前提となっています。
- 適切な経営管理を行う経営責任者がいること
- 技術的な管理を行う専任技術者がいること
- 営業所がきちんと機能していること
今回のケースでは、この3つすべてに虚偽の申請があったため、建設業の健全性を損なう重大な違反と判断された訳です。
事例3
処分の原因となった事実
代表取締役が、刑法 第204条の規定により罰金20万円の略式命令を受け、令和3年4月27日にその刑が確定した。これにより、建設業法第8条第12号に定める欠格要件に該当していたにもかかわらず、令和4年8月31日にとび・土木工事業に係る建設業許可を申請する際、及び令和5年11月15日に解体工事業に係る建設業許可を申請する際に、当該欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書等を提出し、いずれにおいても許可を取得した。
処分の内容
建設業の許可の取消し
解説
代表取締役が、建設業の許可を受けられない「欠格要件」に該当していたのに、虚偽の申請をして許可を取得していた。
代表取締役が「傷害罪(刑法204条)」で罰金刑を受けていた
令和3年4月27日に罰金20万円の略式命令を受け、刑が確定
この時点で「欠格要件」に該当(建設業法第8条第12号)していた。
にもかかわらず、許可申請時に「欠格要件に該当しない」と虚偽の誓約書を提出。
建設業許可には「誠実性」が求められています。建設業法では、許可を受けるために「欠格要件」に該当しないことが条件となっています。
暴力団関係者や重大な法違反をした人が、建設業を営むことを防ぐために過去に一定の刑事処分を受けた人は、一定期間「建設業の許可を受けられない」という規定があります。

2025年営業停止
2025年の建設業許可取り消しの件数は、21件でした。その詳しい内容の代表的な事例について固有名詞なしで解説します。
事例1
処分の原因となった事実
民間工事において、特定建設業の許可を有していないにも関わらず、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことは、同法第16条第2号の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。
同工事において、同法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、政令で定める金額以上の下請契約を締結したことは、同法第28条第1項第6号に該当する。
処分の内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年3月4日から令和7年3月10日までの7日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て
解説
建設業では、下請契約の金額によって「一般建設業」と「特定建設業」の許可が必要になります。
特定建設業の許可を持っていないのに、政令で定められた金額以上の下請契約を結んだ ため、建設業法第16条に違反しました。
特定建設業許可とは、建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請業者が取得する許可です。下請けに出す代金の総額が一定額以上になると必要になります。
無許可の業者に、大規模な下請工事を発注したことも違反に該当します。
特定建設業の許可は「大規模な下請負工事」を管理するために必要です。
一般建設業:小規模な工事の下請契約を結ぶことができる
特定建設業:大規模な工事の下請契約を結ぶことができる
特定建設業の許可がない会社が、政令で定められた金額以上の下請契約を結ぶと違法になります。さらに、許可のない業者に、政令で定められた金額以上の工事を発注するのも違法です。
特定建設業と一般建設業との違いは、下請けに出す建設業者が発注者から直接工事を請け負っている「元請」であるか否かです。 発注者から注文を受けて自ら施工する場合は、一般・特定どちらでも制限はありません。 また、下請として請け負っている場合も特定建設業の許可を取得する必要はありません。
請負金額が500万円以上の建設工事を請け負うためには「一般建設業許可」を取得することが必要です。
さらに元請業者が下請業者へ発注する建設工事の合計額が4,000万円以上となるときは、「特定建設業許可」を取得しなければなりません(建築一式工事では6,000万円以上)。
事例2
処分の原因となった事実
- 複数の民間発注のマンション新築工事において、以下の建設業法に違反する行為を行った。
- (1) 法第3条第1項の規定に違反して、法施行令第1条の2第1項で定める金額以上の請負契約を締結した。
- (2) 法第16条第1項の規定に違反して、法第3条第1項第2号に規定する法施行令第2条に定める金額以上となる下請契約を締結した。
これらのことは法第28条第1項2号及び同条第2項第2号に該当する。
処分の内容(詳細)
営業停止(14日間) 停止を命じる範囲 建築業に関する営業のうち、民間工事に係るもの
解説
この建設業者は、マンションの新築工事において、建設業法のルールを守らずに契約を結んだため、14日間の営業停止処分を受けました。
(1)無許可で高額な工事を請け負った(建設業法第3条第1項違反)
建設業法では、一定の金額以上の工事を請け負うには、国や都道府県から「建設業の許可」を受ける必要があります。
今回のケースでは、その許可を持たずに高額なマンション工事の契約を結んでしまったため、違反となりました。
(2)許可が必要な金額の下請契約を結んだ(建設業法第16条第1項違反)
建設業者が下請業者に工事を発注する際、一定の金額以上になる場合には、発注する側・受注する側の両方が建設業の許可を持っている必要があります。
しかし、この建設業者は必要な許可を持たない下請業者と契約を結んでしまったため、違反となりました。
事例3
処分の原因となった事実
当該建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分の内容(詳細)
1 停止を命ずる営業の範囲 ○○県、○○府における管工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。
2 期間 令和7年2月19日から令和7年3月12日までの22日間
解説
工事現場に必要な資格を持っていない人を「主任技術者」や「監理技術者」として配置したために違反となりました。
建設業法では、工事の品質や安全性を確保するため、一定の資格を持った「主任技術者」または「監理技術者」を配置することが義務付けられています。
主任技術者とは、一般的な工事現場で必要な技術責任者です。国家資格(例:管工事施工管理技士)や一定の実務経験が必要になります。
監理技術者とは元請業者が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の工事を請け負う場合に必要な責任者です。主任技術者よりも上位の資格で、より高い技術や管理能力が求められます。
事例4
処分の原因となった事実
自治体が発注者である工事において、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当するため内装解体工事は内装仕上工事業に該当するところ、建設業法第3条第1項の規定に違反して、内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分の内容
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分
営業停止期間:令和7年2月6日から同月28日までの23日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
解説
違反の内容としては許可がない工事を請け負った(無許可営業)ことにあり、この建設業者は、自治体が発注した工事で「内装解体工事」を請け負いましたが、建設業法では「内装解体工事」は「内装仕上工事業」の許可が必要とされています。
この建設業者は「内装仕上工事業」の許可を持っていなかったため、許可が必要な規模の工事を無許可で請け負ったことが違反となりました。(建設業法第3条第1項違反)
建設業を営むには、工事の種類ごとに許可を取得する必要があります。許可がない業種の工事を一定規模以上で請け負うと、無許可営業となります。
事例5
処分の原因となった事実
請け負った民間工事において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に違反し、令和5年5月17日に奈良地方裁判所から罰金の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分の内容
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事以外に係るもの 2 期間 令和7年1月21日から令和7年1月27日までの7日間
解説
請け負った民間工事の現場で、廃棄物処理法に違反しました。
建設現場では、発生する廃棄物(がれきや木材、コンクリートなど)を適切に処理する義務があります。違法に廃棄すると、環境への悪影響や不法投棄の問題が発生し、社会的に問題になります。
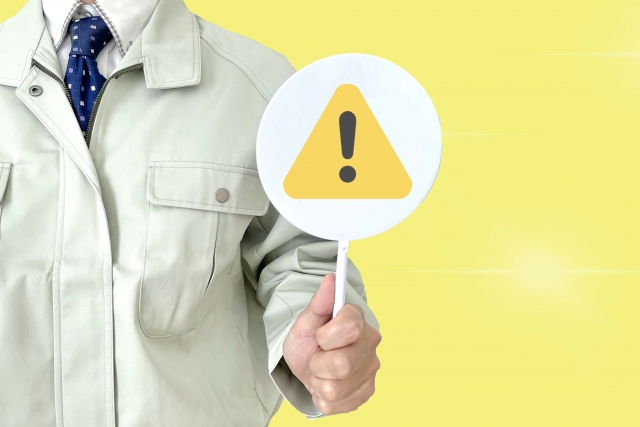
2025年指示
2025年の建設業許可取り消しの件数は、26件でした。その詳しい内容の代表的な事例について固有名詞なしで解説します。
事例1
処分の原因となった事実
建設業法第27条の23第1項の規定に違反し、有効な経営事項審査結果を有しないまま、令和6年12月に高知市上下水道局発注の工事の請負契約を締結した。
処分の内容
今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。
(1) 建設業法第27 条の23 に規定される建設工事を請け負おうとする場合には、前年度の経営事項審査の有効期間が満了する日までに審査を受け、経営事項審査の有効期間に切れ目ができないようにすること。
(2) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
(3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。
解説
経営事項審査の有効期限が切れた状態で、自治体の工事を請け負う契約を結んでしまいました。
経営事項審査とは、公共工事を受注するためには、「経営事項審査(経審)」を受けて、審査結果を有効にしておく必要があります。これは、会社の経営状況や施工能力が適正であるかを確認する審査です。
審査の有効期間は 1年間 なので、毎年更新しなければなりません。しかし、この更新を怠り、経審の有効期限が切れた状態で工事契約を結んでしまい建設業法第27条の23第1項 に違反する行為となりました。
公共工事では、業者の信用性や施工能力が非常に重要です。そのため、経審を通じて適格な業者だけが契約できるようにしています。
最新の建設業法違反ニュース
2025年3月11日、NHKで下記の違反ニュースが報道されました。
国や自治体の許可を受けずにリフォーム工事を行ったとして、警視庁は複数の悪質リフォーム業者を統括していたとみられる40代の容疑者ら4人を建設業法違反の疑いで逮捕しました。
容疑者は「スーパーサラリーマン清水」と名乗り、派手な生活ぶりをSNSに投稿してメンバーを集めていた疑いがあるということです。
建設業許可なしで500万円以上のリフォーム工事を請け負っていたとして、建設業法違反の容疑で逮捕されました。