「煩雑な建設業許可を取らずに工事を請け負う方法はないか?」「抜け道や抜け穴があるなら知りたい」「バレなければ問題ないのでは?」といった疑問をお持ちの方もいるかもしれませんが、建設業法は、建設工事の適正な施工を確保して発注者を保護し、建設業の健全な発達を促進することを目的とした重要な法律です。法律を無視した営業を行うと、重大な罰則を受ける可能性がありますので注意が必要です。不安な場合は、静岡の行政書士法人アラインパートナーズにご相談ください。それでは詳しく解説します。
お願い!:恐れ入りますが、お問い合わせについては、静岡県の方で建設業許可に関する内容でお願い致します。
建設業法とは
建設業法は、建設業の適正な運営と公共の利益を守るための法律です。この法律は、建設工事の請負契約や施工に関する基準を定めてあり、業者が適切な資格や能力を持っていることを保証することで工事の品質や安全性を確保しています。
建設業許可
建設業許可とは
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要な行政による許認可のことです。建設業許可によって、業者が法的な基準を満たしていることが証明されて、信頼性の高い営業をすることができます。
建設業許可は、工事の種類に応じて29種類に分かれており、請け負う工事の種類に応じた許可を取得する必要があります。
また、許可には特定建設業と一般建設業の区分があり、下請契約の金額によってどちらの許可が必要になるかが異なります。
特定建設業
発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の額(税込)の総額が4,500万円以上となる下請契約を締結する場合に必要です。
一般建設業
特定建設業に該当しない場合です。
許可の取得要件
建設業許可を取得するには、次の要件を満たす必要があります。
経営業務の管理責任者の配置
経営経験を有する者を配置することが求められます。
専任技術者の配置
一定の資格や経験を持つ技術者を営業所ごとに配置する必要があります。
財産的基礎の確保
一定の資本金や自己資本を有していることが必要になりす。
欠格要件(誠実性の確保)
過去に不正行為や法令違反がないことが求められます。

許可を取得せずに建設業を行う方法
建設業法では、請負代金500万円(税込)未満の工事であれば、許可なしで請け負うことができますが、これを悪用し、実質的に500万円を超える工事を行うための抜け道を使う手口もあります。
工事を複数に分割する方法
これは、1つの工事を意図的に複数の契約に分けることで、各契約を500万円未満に抑える手法です。
例えば、同じ建物の工事を基礎工事490万円と仕上げ工事480万円のように分けて契約することで、許可が不要な工事に見せかける方法です。
しかし、この方法は行政側は行政側の想定内の方法(よくある方法)なので違法とみなされる可能性が高いです。行政は契約の実態を調査して、複数の契約が実際には一体の工事であると判断されると、合計金額が500万円を超えているため違法とされてしまいます。まず、バレてしまうと思ってください。
バレる理由
契約書の内容や工事の発注元の証言から、工事が分割されているだけと判断されるわけです。
発注者が同じであり、工期や施工業者が連続しているため、実態として一つの工事と認定されてしまいます。
摘発事例
過去に、複数の契約を細かく分けていた建設業者が、実態として一括の契約であったと判断され、行政処分を受けた事例があります。
特に、公共工事においてこの手法が悪用された事例があり、指名停止処分や罰則が科された事例もあります。
材料費を分ける方法
もう一つの手口として、工事費と材料費を別契約にしてしまうことで、工事代金を500万円未満に抑える方法があります。
例えば、工事費460万円にして材料費をわけて200万円のように、工事自体の金額を低く見せかける方法です。
しかし、この手口も行政側にも周知されていて、実態としては一つの工事とみなされて、違法行為と判断されてしまいます。そもそも規定では「材料費を含む」とされています。これもバレると思っておいてください。
建設業法上、請負契約の実質的な金額を基準に判断されるために材料費を分けても免れることはできません。
バレる理由
契約書や請求書の内容を確認すれば、意図的な分割が発覚します。発注者が同じ場合、工事費と材料費を分ける合理的な理由がないと判断されます。
また、税務調査などで帳簿をチェックされて資金の流れから実態が判明する場合もあります。
摘発事例としては、この工事費を500万円未満にして、材料費を別契約にする方法で営業を続けていましたが、税務調査と行政の調査が入り、違法な契約分割と判断され、建設業法違反で処分を受けたという事例があります。
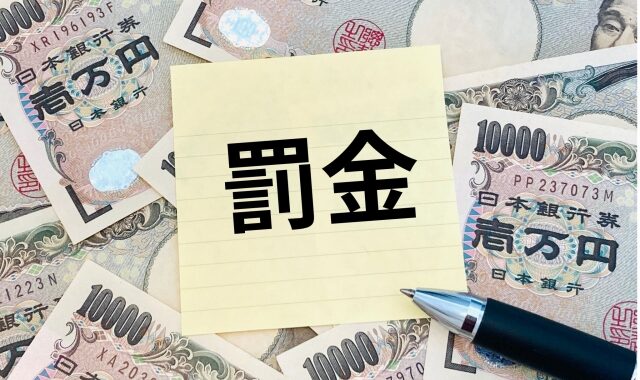
抜け道や抜け穴はバレないの?捕まらない?
無許可での営業や虚偽の申請など、建設業法の違反行為は厳しく取り締まりされています。
無許可営業の事例
たとえば、建設業許可を持たずに軽微な工事の基準額を超過した請負契約を締結した業者が、営業停止処分を受けています。
虚偽申請の事例
たとえば、建設業許可の申請において虚偽の工事実績を提出し、逮捕された事例があります。
許可要件違反の事例
取締役が建設業法違反により罰金刑を受けて、その結果、建設業許可の取消処分を受けた事例があります。
これらの事例からも分かるように、違反行為は高い確率で発覚してしまい、厳しい処分が科されます。
無許可営業や虚偽申請などの抜け道を試みることは、リスクが高く、結果的に罰則を受ける可能性が高くなります。
無許可営業が発覚する事例のまとめ
発注者からの通報
工事の質が悪かったり、トラブルが発生したりした場合、発注者が無許可であることを知り、行政機関に通報する場合があります。
下請業者からの情報提供
下請業者が、元請業者が無許可であることを知り、情報提供する場合があります。
同業者からの通報
同業者が無許可営業の事実を知り、通報することがあります。
行政機関の調査
行政機関は、建設業者の情報を収集しており、無許可営業の疑いがある業者に対して調査を行うことがあります。
税務調査
税務調査の過程で、建設業許可が必要な工事を無許可で行っている事実が発覚することがあります。
違法な抜け道は最終的にバレる!
これらの手口は一時的には許可なしで工事を請け負えるようになるかもしれませんが、行政のチェックや税務調査、元請けや発注者の証言によって発覚する可能性が非常に高いです。まず、バレてしまうと思っておいてください!
発覚すると、営業停止処分、許可取得の禁止(一定期間)、罰金刑など、事業継続に大きな支障をきたすことになります。
許可なしで建設業を行うことはリスクが高く、正規の手続きを踏んで許可を取得する方が、結果的に安全で長期的な経営が可能になります。手続きは、煩雑でたいへんですが、静岡の行政書士法人アラインパートナーズに相談してみてください。
無許可営業の罰則
- 建設業法に違反して無許可で建設業を営んだ場合、以下の罰則が科せられることがあります。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)
- 法人の場合は、代表者や担当者も同様の罰則を受ける可能性
- 許可の申請をしても、一定期間許可を受けることができなくなる
- 社会的信用を失い、事業の継続が困難になる可能性
なお、その他にも建設業法違反の法令文には、次のようなものがあります。
一括下請負(工事の丸投げ)の禁止(建設業法第22条)
許可なく一定額を上回る契約を結んだ場合に、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる(建設業法第47条)
第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
一の二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者
三 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
虚偽記載した場合(建設業法第50条)
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
罰金について(建設業法第52条)
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条第一項から第三項までの規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつた者
四 第二十七条の二十四第四項又は第二十七条の二十六第四項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
五 第三十一条第一項又は第四十二条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第三十一条第一項又は第四十二条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
主任技術者や監理技術者も配置しないといけません。違反になります!
(過料について(建設業法第55条))
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
二 正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
三 第四十条の規定による標識を掲げない者
五 第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者
標識も掲げないといけません。




