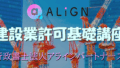静岡の行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務のご質問などの経験に基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識を信頼性が高く権威のある静岡県の手引きを基に、アラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを加えてわかりやすく解説しました。
建設業法第3条は、建設業許可制度の最も重要な条文です。500万円基準は、個人事業者や小規模業者などが許可の要不要を判断する場合の基準となります。建設関係の請負金額の構成や契約実態を正確に把握して、適切に許可が必要かどうか判断する必要があります。それでは、基礎的な事柄を中心に詳しく解説します。
お願い!:恐れ入りますが、お問い合わせについては、静岡県の方で建設業許可に関する内容でお願い致します。
建設業法とは
建設業法(昭和24年法律第100号)は、建設工事の適正な施工と発注者の保護を目的として制定された法律です。
施工体制の整備、技術者の配置、下請取引の適正化などを定めており、公共工事や民間工事なのかを問わず、建設業界全体の健全な発展を図ることを目的としています(建設業法第1条)。
この法律にメインで書かれているのが「建設業許可制度」であり、一定規模以上の建設工事を請け負う場合は、国(国土交通大臣)、または都道府県知事の許可を受けなければならないことが明記されています。この法律に基づいて、一定規模以上の建設工事を請け負う業者に対して「建設業許可」の取得を義務付けているのです。
こちらが建設業法からの条文の引用です。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

建設業法第3条とは
建設業法第3条は、建設業を営む場合に「建設業許可が必要となる場合」を定めた条文です。条文では次のように規定されています。
(建設業の許可)建設業法第3条第1項
建設業を営もうとする者は、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、他人から建設工事の請負を引き受けて営業を行う場合においては、建設業の許可を受けなければならない。
ただし、第3条第3項により、軽微な建設工事については例外として「許可を受けなくてもよい」とされています。この「軽微な建設工事」に該当するかどうかを判断する基準が、500万円基準です。条文には例外が設けられており、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要とされています。この「軽微な建設工事」を判断するための基準こそが、次に解説する「500万円基準」などです。
なお、ここで問い合わせなどで、よく質問や誤解があるのが、この500万円基準は消費税込みということです。500万円となると消費性は50万円であり、消費税が入っているかどうかという確認が必ず必要になってきますので注意が必要です。
建設業法第3条の引用です。
建設業の許可
ア 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
イ 「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては、500万円未満、建築一式工事にあっては1,500万円未満または延べ面積が1,500平方メートル未満の木造住宅の工事をいいます。
建設業許可とは
建設業許可とは、一定の技術的や財務的要件を満たす者が、国または都道府県から建設業を営むことを認められる行政上の許可制度です。
建設業許可は工事の種類ごとに区分されており、全部で29業種(土木一式工事・建築一式工事・大工工事・電気工事など)に分かれています。
また、建設業許可は「営業所ごと」ではなく「法人または個人事業者単位」で付与されます。
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業の許可を受けなければなりません。
これは法人であるか個人事業主であるかを問わず、また元請負人であるか下請負人であるかを問わず、さらにその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、請負として建設工事を施工する者は、許可を受けることが必要となります。
社会的信用の向上については、建設業許可業者は一定の要件(財産的基礎、技術力など)を満たしているため、発注者や金融機関からの信用が高まることになります。ある程度技術力があって、倒産しにくい財力があるという判断をされやすくなります。
なお、公共工事ですが、公共工事への参加が可能になります。原則として、公共工事の入札に参加するためには建設業許可が必要となります。
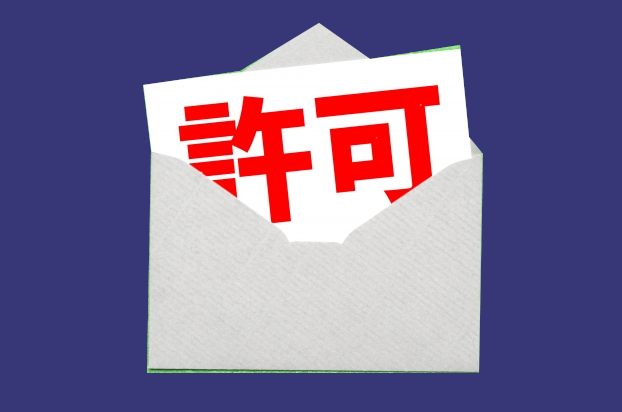
500万円基準
建設業法第3条第3項および施行令第1条により、軽微な工事とは次のように定義されています。
建築一式工事の場合
建築一式工事の場合であれば、1,500万円(消費税込み)未満となります。
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとで建築物を建設する工事のことで、元請け業者として複数の専門工事(基礎工事、大工工事、内装工事など)をまとめて発注・管理し、建物を完成させる工事のことです。戸建住宅の新築やビル建設、建築確認を必要とする大規模な増改築・改修工事などが含まれます。
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業の許可を受けなければなりませんが、「1件の請負金額が1,500万円未満(消費税を含む)、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事」となっています。
「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものをいいます。「住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。
建設業法第3条の例外である「軽微な建設工事」に該当するかどうかを判断する基準が「500万円基準」です。この基準を超える工事を請け負う場合は、建設業許可が必須となります。
建築一式工事以外の工事(土木・大工・電気など)
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業の許可を受けなければなりませんが、ただし、次に揚げる「軽微な建設工事」(小規模な建設工事)のみを請け負う者は、必ずしも建設業の許可を受ける必要はありません。
しかしながら、重要なのは請負契約の書面による締結等、建設業者と同様に法の対象となっています。
1件の請負金額が500万円未満(消費税を含む)
500万円(または1,500万円)を超える請負工事を1件でも受注する場合は、建設業許可が必要です。この基準を超えて無許可で請け負うと、「無許可営業」として処罰の対象となります。
ほとんどの建設業許可取得の方は、この500万円基準となります。一人親方の個人事業主や中小の建設業者の方は、500万基準になることがほとんどです。
材料費での判断
建設業許可基準の判断として、注文者が材料を提供して、請負代金の額に材料提供価格が含まれない場合においては、その市場価格、および運送費を加えた額となります。
たとえば、請負契約代金(税込み) 420万円で材料費(支給)(税込み) 100万円だったとすると工事費合計金額として520万円なり、建設業許可は必要となります。この場合、請負契約は税込み500万円未満であるが、注文者から支給された材料費100万円を合計すると税込み520万円となり、許可が必要な建設工事となるのです。
要するに材料費も含みますよということです。仮に無料で施主から支給された場合であっても適切な市場価格をつけて判断される可能性がありますよということです。
契約内容での判断
同一の建設業を営む者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額となります。法令第1条の2第2項、つまり、建設業許可を逃れるために契約を分割した場合は違法となります。
同一の建設工事を請け負うにあたり、作為的に複数の契約に分割して、それぞれの契約額を500万円未満にしても、合計額で判断されます。分割に「正当な理由」がない限り、許可が必要となりますので注意が必要です。
運送費でに判断
原則として運送費も請負金額に含まれます。建設業法でいう請負金額とは、請負契約に基づき発注者が支払う総額(消費税を含む)のことを指していますので、工事の施工に必要なすべての費用が対象となります。
したがって、運送費が工事の一部として契約書に含まれている場合には、資材や機材を運搬することが工事遂行に必要な行為である場合、運送費も請負金額に含まれる扱いになります。
ただし、運送業者(運送許可を有する者)が、純粋に運送だけを行う契約である場合、建設工事とは別個の契約書・発注書で運送費が明確に分離されている場合、請負者自身が施工に関与せず、単に資材を配送するだけの場合には、工事契約とは別に独立した運送契約として発注されていれば、その運送費は「建設工事の請負金額」には含まれません。
重要なポイント
1件の請負金額が500万円未満(消費税を含む)の契約では、建設業許可は必要ありませんが、請負金額には、材料費・人件費・運送費・消費税をすべて含みます。複数工事を分割して請け負うことで500万円未満に見せかける行為は、実態により違法と判断されることがあります。
その他注意事項
浄化槽工事、または解体工事を請け負うためには、工事1件の請負金額の額が税込み
500万円未満の工事であっても、「浄化槽法に基づく登録若しくは届出」、または「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく登録が必要となります。
なお、建設リサイクル法に基づく登録については、建設業者が「土木工事業」、「建築
工事業」又は「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は不要です。
建設業許可の有効期間と許可区分
建設業許可の有効期間は5年間で、引き続き営業するためには期間満了前に「更新申請」を行う必要があります(法令第5条の3)。
大臣許可と知事許可
建設業許可には、大臣許可と知事許可の区分があります。
大臣許可は複数の都道府県に営業所がある場合、営業所の所在地によって区分されるもので、受注できる工事の金額や範囲に制限はありません。
知事許可は一つの都道府県内に営業所がある場合です。
なお、知事許可と大臣許可のいずれであっても、営業や施工できる地域に制限はありません。
一般建設業と特定建設業
許可の種類は一般建設業と特定建設業に分かれています。一般建設業は下請代金が5,000万円(建築一式は8,000万円)未満の下請契約まで請け負えます。
特定建設業は5,000万円(建築一式は8,000万円)以上の下請契約を締結する場合に必要となります。
下請契約の締結に係る金額について、令和7年2月1日より、建築工事業の場合は7,000万円から8,000万円に、それ以外の場合は4,500万円から5,000万円に、それぞれ引き上げられましたのでご留意ください。
令3条の使用人とは
令3条の使用人とは、建設業法施行令第3条に規定されている営業所の代表的な地位にある使用人を指します。
実務上は「支店長」や「営業所長」など、現場で契約行為を行う権限を持つ人物が該当します。
令3条の使用人は、許可申請において重要な役割を持ちます。たとえば、知事許可業者が他県に営業所を設置する場合、その営業所に配置する「令3条の使用人」が存在することが、許可区分(大臣許可か知事許可か)を判断する要素になります。
建設業法施行令からの引用です。
(使用人)
第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。
一方で、経営業務の管理責任者は、営業所全体の建設業の経営業務を総合的に管理する責任者であり、本店に配置されることが多く、令3条の使用人の経験でもなれる場合もあります。

建設業法第3条違反
建設業法第3条に違反して無許可で建設業を営んだ場合は、建設業法第45条第1号により次の罰則が科せられます。
無許可営業の罰則
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(または併科)
さらに、無許可業者が請負契約を締結しても、発注者との間で契約自体は民法上有効とされるものの、行政上は重大な違反行為となり、公共工事の入札資格の停止や将来の許可申請に影響することがあります。
建設業法第45条の引用です。
第四十五条 登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の拘禁刑に処する。
2 前項に規定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
3 第一項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
4 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。