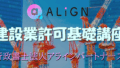建設業法第3条を中心に「建設業許可制度の基本」をわかりやすく詳しく解説します。建設業許可は、基本的にはすべての建設業者が遵守すべき制度であり、違反すれば営業停止や罰則の対象にもなります。その中でも「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区分は、元請と下請の関係に関わる重要なポイントであり、さらに「大臣許可」と「知事許可」の許可区分もわかりやすく詳しく解説します。
お願い!:恐れ入りますが、お問い合わせについては、静岡県の方で建設業許可に関する内容でお願い致します。
建設業法とは
建設業法(昭和24年法律第100号)は、建設工事の適正な施工と発注者の保護を目的とする法律です。建設業は多額の費用を費やすことになり、しかも公共性が高いことから、国や自治体が一定の基準を定めて建設業者を監理監督しています。
建設業法の法律の目的(第1条)には次のように定められています。
「建設工事の適正な施工を確保し、発注者の保護を図るとともに、建設業の健全な発達を促進する」
建設業法は「誰でも自由に工事を請け負えるわけではない」という前提のもとに、技術力・財務基盤・法令遵守体制を持つ業者だけが建設業として営業できるようにする法律です。
こちらが建設業法からの引用です。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
お願い!:恐れ入りますが、お問い合わせについては、静岡県の方で建設業許可に関する内容でお願い致します。
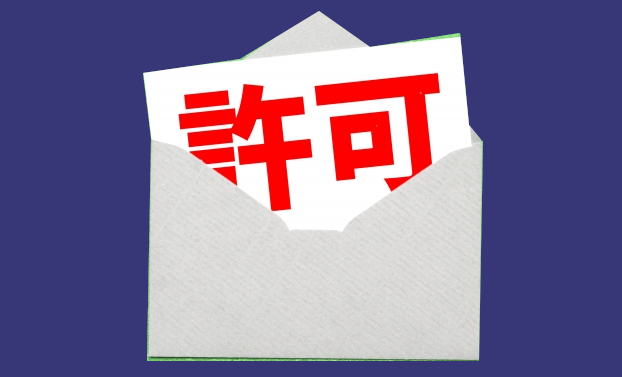
建設業許可とは
建設業許可とは、建設工事の請負契約を業として行うために必要な国、または都道府県の許可です。
- 建設業許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者が配置されていること
- 営業所技術者(旧専任技術者)が配置されていること
- 財産的基礎または金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
建設業許可を取得して初めて建設業者として営業できますし、請け負う金額や工事の種類によっては、「一般」と「特定」に区分されます。これが建設業法第3条に定められています。
建設業法第3条の引用です。
建設業の許可
ア 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
イ 「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては、500万円未満、建築一式工事にあっては1,500万円未満または延べ面積が1,500平方メートル未満の木造住宅の工事をいいます。
経営業務の管理責任者とは、建設業の営業所において、建設業の経営業務を総合的に管理し、対外的に責任を負う役職です。営業所技術者(旧専任技術者)は、建設業許可を持つ営業所ごとに配置が義務付けられている、一定の資格や経験を持つ技術者のことです。
建設業法第3条とは
建設業法第3条は、建設業を営むための「許可の義務」を定めた条文です。条文の冒頭部分は次のとおりです。
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
ここで重要なのは「建設業を営もうとする者」という記述です。一度だけ工事を請け負う場合は「業として」に該当しないこともありますが、反復継続的に工事を請け負う場合は必ず建設業許可が必要です。
さらに第3条では、請け負う工事の形態によって「一般建設業」と「特定建設業」および「大臣許可」と「知事許可」に分かれることが規定されています。
建設業法第3条第1項第1号・第2号とは
第3条第1項は、許可の区分を明確にする規定です。
第1号 一般建設業の許可
発注者から直接工事を請け負う場合で、下請けに出す金額が一定規模を超えない工事を行う業者のことです。
第2号 特定建設業の許可
特定建設業許可(第1項第2号)は、発注者から直接請け負った1件の工事につき、総額5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)を下請けに出す場合に必要となる許可です。
「特定」という名のとおり、一般建設業よりも厳しい財産的要件や技術的要件が課されます。これは、多額の工事を下請業者に発注する元請業者に対して、その下請業者を適切に指導や監督をして保護する能力を担保するためです。
元請として多くの下請業者に工事を発注する場合は「特定建設業」、そうでなければ「一般建設業」となります。一人親方(個人事業主)や多くの中小の建設業者は一般です。

一般建設業許可とは
一般建設業許可は、原則として元請として工事を請け負う場合、または下請として工事を請け負う場合の基本的な許可です。許可の要件は特定建設業に比べて緩和されており、多くの事業者が取得しています。
しかし、特定建設業に関する規定により、一般建設業許可業者が元請として工事を請け負う場合、その工事について下請けに出せる金額に上限があります。
- 一般建設業許可は次のような特徴があります。
- 下請けに出す工事の金額が「一定規模(5,000万円/8,000万円)」以下であること
- 元請として請け負っても、下請への発注が比較的少額
- 財務要件は特定建設業ほど厳しくない
建設業を始める場合、多くの業者がまずは一般建設業許可を取得します。元請・下請のいずれも可能ですが、大規模な下請を伴う工事を行う場合は特定建設業許可が必要になります。
特定建設業許可とは
特定建設業許可は、大規模な工事を元請として請け負い、多くの下請業者に発注する事業者が対象です。
特定建設業許可(第1項第2号)は、発注者から直接請け負った1件の工事につき、総額5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)を下請けに出す場合に必要となる許可です。
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとで建築物を建設する工事です。具体的には、戸建て住宅の新築やビルの建設など、複数の専門工事をまとめて管理して一棟の建物を完成させる大規模で複雑な工事のことです。
「特定」という名の通り、一般建設業よりも厳しい財産的要件や技術的要件が課されます。これは、多額の工事を下請業者に発注する元請業者に対し、その下請業者を適切に指導や監督を行い、保護する能力を担保するためです。
特定建設業許可は「下請を多く使う元請業者のための許可」であり、そのため責任も大きくなります。
なお、請契約の締結に係る金額について、令和7年2月1日より、建築工事業の場合は7,000万円から8,000万円に、それ以外の場合は4,500万円から5,000万円に、それぞれ引き上げられました。
特定建設業許可と下請け保護
特定建設業許可制度には、下請け保護の考え方があります。建設業界は多重下請構造となっており、資金力の弱い下請業者が不利益にならないようにするため、特定建設業者には監理技術者を設置することによって、施工管理の強化をして、下請契約の適正化、たとえば、書面交付や支払期日遵守などを実施しています。
また、下請代金支払の保証制度の整備や下請への不当な圧力や契約変更の禁止のような義務や制限が設けられています。
特定建設業許可は、大規模工事の元請業者が下請を適切に管理や保護するための制度でもあります。
一般と特定のまとめ
一般と特定の違いは分かりづらいところがあるので、静岡県の手引きに沿って、違う角度からまとめておきます。
特定建設業許可は、発注者から直接請け負う1件の建設工事について、その工事の全部または一部を、下請代金の額が税込み5,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合の許可です。建築一式工事の場合は、税込み8,000万円以上と読み替えるということになります。
下請契約が2つ以上ある場合は、その合計額となり、消費税を含んでおり、元請負人が提供する材料などの価格は含みません。
一般建設業許可は、特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可となります。
一次下請発注総額によっては、特定建設業の許可が必要となっている要件は、発注者から直接請け負った元請業者に対してのみ求めているものであり、一次下請負以下として契約されている建設業者は、このような制限はありません。
なお、工事の規模の大小は関係ありません。比較的規模の大きい工事を元請として受注した場合でも、その全部を元請にて自社施工するか、一次下請発注総額が税込み5,000万円未満(建築一式工事の場合は税込み8,000万円未満)であれば、特定建設業の許可は不要になります。
建設業法第3条第2項・第3項
建設業法第3条の第2項と第3項は、許可を与える主体である許可の行政庁を定めており、許可を「大臣許可」と「知事許可」に区分しています。
(第2項)
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(第3項)
前項に該当しない者は、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

大臣許可と知事許可
建設業法第3条の引用です。
第二章 建設業の許可
第一節 通則
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
大臣許可とは
国土交通大臣の許可(大臣許可)は、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合に必要となります(第2項)。
「営業所」とは、本店や支店のほか、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。例えば、静岡県と神奈川県にそれぞれ営業所を設けている事業者は、国土交通大臣に許可を申請することになります。
知事許可とは
都道府県知事の許可である知事許可は、1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合に必要となります(第3項)。
営業所が静岡県内にしかない場合は、静岡県知事の許可を受けます。注意が必要なのは、工事の場所ではなく、営業所の所在地によって行政庁が決まる点です。知事許可であっても、他県での工事を請け負うことはできます。
ポイント
国土交通大臣許可(大臣許可)は国土交通大臣が管轄しており、2つ以上の都道府県に営業所を設置できます。東京に本店があって、静岡に支店がある場合などです。
都道府県知事許可(知事許可)は都道府県知事が管轄して1つの都道府県内のみで営業となります。たとえば、静岡県内のみに営業所がある場合などです。
なお、営業所とは単なる倉庫や名目上の事務所ではなく、建設工事の契約や営業活動を行う拠点を指しています。実態として営業行為を行っているかどうかで判断されます。重機や資材置き場ではダメです。
なお、大臣許可は、静岡県庁ではなくて国交省の出先機関である中部地方整備局となります。
中部地方整備局 建政部計画・建設産業課
〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館
電話:052(953)8572
管轄県:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
知事許可は、静岡県庁です。
静岡県 土木部建設業室
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話:054(221)3058
県境をまたいだ営業について
当事務所にもよくある質問で、「静岡県知事許可だと隣県の愛知県や神奈川県でで工事ができないのではないのですか?」という問い合わせがありますが、そんなことはありません。
許可の区分は営業所の所在地で決まります。
知事許可は、営業所が1つの都道府県内のみにありますが、工事は全国どこでも営業ができます。
大臣許可の場合でも営業所が2つ以上の都道府県にまたがってあったとしても、工事は全国どこでもできます。
静岡県知事許可の場合で、愛知県や山梨県の工事を請け負うことはまったく問題ありませんが神奈川県内に新たに支店や営業所をつくる場合は、静岡県と神奈川県の2つの都道府県に営業所を持つことになるため、あらためて国土交通大臣許可を取得し直す必要があります。
まとめ
建設業法第3条は、一般・特定という工事の規模と下請けへの関わり方による区分と、大臣・知事という営業所の所在地による区分を定めています。事業計画に応じて適切な許可を取得することが、建設業を適法かつ健全に営むための第一歩となります。これらの要件でわからないことがあれば、静岡の建設業許可専門の行政書士法人アラインパートナーズに相談してください。静岡県内であれば無料でご相談を承ります。