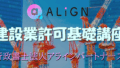静岡の行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務のご質問などの経験に基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識を信頼性が高く権威のある静岡県の手引きを基に、アラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを加えてわかりやすく解説します。
建設業許可の取得では、人的要件・財務要件・法令遵守が総合的に審査されます。それでは詳しく解説します。
お願い!:恐れ入りますが、お問い合わせについては、静岡県の方で建設業許可に関する内容でお願い致します。
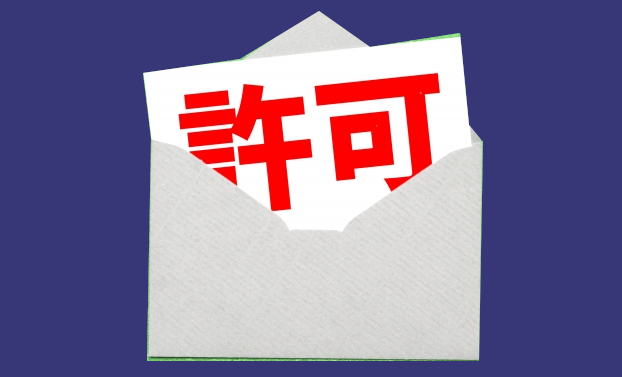
建設業許可とは
建設業許可は、建設業法第3条に基づいて一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な国または都道府県(静岡県知事)の許可のことです。
建設業法では、税込み500万円未満の工事など「軽微な建設工事」を除いで、元請・下請を問わず建設工事を請け負う場合には、建設業許可が義務となっています。
建設業許可は、下請に一括下請を出せない一般建設業許可と下請に一括して工事を発注できる特定建設業許可の2種類がありますが、さらに29業種ごとに区分されていますので業種ごとの許可となります。
許可を受けるためには、建設業法第7条(法人・個人共通)および第15条(特定建設業許可の追加要件)に定められた要件を満たす必要があります。
建設業法第七条(許可の基準)からの引用です。
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
なお、第十五条は特定建設業許可の基準(要件)となります。
(許可の基準)
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

建設業許可の5つの基準(要件)
建設業法第7条では、次の5つの要件(基準)が定められています。これらをすべて満たさなければ、建設業許可は取得できません。
1.経営業務の管理責任者がいること
2.営業所ごとに専任の技術者(営業所技術者・旧専任技術者)がいること
3.誠実性があること
4.財産的基礎または金銭的信用があること
5.欠格要件に該当しないこと
それでは、それぞれを詳しく解説します。
経営業務の管理責任者(経管)
概要
建設業法には建設業を安定的かつ適正に営むためには、経営経験を持つ責任者が必要という考え方があります。経営業務の管理責任者(経管)を常勤で配置することが求められています。
経営業務管理責任者とは、建設業の「経営」と「業務」を総合的に管理する責任者のことです。建設業許可を取得するためには、この経営業務の管理責任者が主たる営業所に常勤していることが必須です。この一定の経営経験を持つこの責任者が不可欠となっています。略称は「経管」です
要件(基準)
経管になるには次のいずれかを満たすことが必要になています(令和2年10月改正後の基準)。
1.経営業務の管理経験
役員・支配人・個人事業主・支店長などで、許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務管理経験を有する者
2.補佐経験者を含む役員構成
例えば3年以上など経営業務を補佐した経験を有する者を含めて、経営を的確に行う体制が整っていること。
3.個人事業主(一人親方)の場合
自ら5年以上建設業を営んだ経験があること。
営業所(専任)技術者
概要
各営業所には、工事内容を理解して適正に施工できる能力を持つ技術者を常勤で置かなければなりません。営業所技術者は、建設業許可を得るために営業所ごとに必ず設置が義務付けられている建設工事の請負契約に関する技術管理を行う技術者の配置が必要になります。
令和6年12月の建設業法改正で、従来の専任技術者という名称から変更されました。営業所にいる技術者ということを強調した格好になりました。
主な役割は、技術的な観点から請負契約の確認や締結を支援して現場の技術者をサポートや監督をすることです。営業所技術者は、原則としてその営業所に常勤し、専ら業務に従事する必要があります。
要件
営業所技術者には、次のいずれかの資格と経験が必要になります。
国家資格の保有
許可を受けたい建設業種に対応した国家資格を持っていることが要件になります。
たとえば、1級・2級施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士、1級・2級技能士などです。
複数の業種にまたがる資格を保有していれば、そのすべての業種で営業所技術者になれます。
指定学科卒業と実務経験
指定学科卒業と実務経験でも要件とすることもできます。
「指定学科」(土木、建築、電気など)を卒業していること。
学歴に応じた期間の実務経験があること。
大学(指定学科卒)であれば3年以上、高等専門学校であれば、3年以上、高校(指定学科卒)は5年以上などです。
10年以上の実務経験
10年以上の実務経験でも要件とすることができます。建設業種に関する技術的な実務経験が10年以上あること。ただし、詳細な実務経験の証明が必要になります。
特定建設業の場合(法第15条)
特定建設業では、下請けへの発注規模が大きいために一般建設業許可より高い資格または経験が必要となります。
誠実性
概要
建設業法第7条第3号に基づき、請負契約を誠実に履行する能力・態度が求められます。これは、社会的信用を維持するための要件です。
建設業法からの引用です。
(許可の基準)
第七条三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
具体例
このような場合は「誠実性を欠く」と判断された場合は許可が下りないことがあります。
談合、虚偽申請、工事代金未払いなど不正・不誠実な行為を行った者や建設業法または関係法令に違反し、処分を受けた者などです。
国交省や静岡県などの行政庁では、過去の行政処分・刑事罰・民事紛争の履歴などから総合的に判断します。
財産的基礎(または金銭的信用)
概要
建設業は前払金や資材購入などで資金需要が大きいため、一定の財務基盤が必要になります。
一般建設業と特定建設業
建設業法第7条第4号、同法第15条第3号(下記)
一般建設業と特定建設業では要件が異なります。建設工事を着手するにあたっては、資材の購入および労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。
また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要になりますので、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎などがあることを許可の要件としています。
特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも厳しくなっています。特定建設業者では多くの下請負人を使用して、工事を施工することが一般的であることや、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていることなどの理由があるからです。
一般建設業の要件(基準)
- 一般建設業の財産的要件は次のいずれかに該当することです。
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業の要件(基準)
- 特定建設業の財産的要件は次のいずれかに該当することです。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
資本金の欠損とは、会社の赤字が累積して資本金まで失われてしまった状態のことです。純資産が資本金や法定準備金を下回ることで生じて、会社の経営基盤が不安定になり、信用力低下や将来の資金繰りの悪化につながる危険信号が出てる状態です。
流動比率とは、企業の短期的な支払い能力を測るための財務指標です。1年以内に現金化できる資産である流動資産を1年以内に返済が必要な負債流動負債で割って、その割合をパーセンテージで示したものです。
建設業法の引用です。
第二節 一般建設業の許可
(許可の基準)
第七条四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
第三節 特定建設業の許可
(許可の基準)
第十五条三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
欠格要件
概要
建設業法第8条に基づいて、一定の違法行為や不正行為を行った者は建設業許可を受けることができません。これは公共性の高い建設業の健全化を目的としているからです。
具体的な内容
たとえば、許可申請書、またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
国土交通大臣や静岡県知事など都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の1から14のいずれかに該当するときや許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
・破産者で復権を得ないもの
・一般建設業の許可、または特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・第28条第3項、または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設工事の施工、もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法の罪、もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
建設業法の引用です。
第八条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
(中略)
七 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(中略)
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者