静岡県では経営事項審査を事業継承や法人成において引き継ぐことが可能です。詳しいタイミングと要件を詳しく解説します。
なお、情報の確認は、静岡県の経営事項審査の手引きで確認済みです。
お願い!:恐れ入りますが、お問い合わせについては、静岡県の方で建設業許可に関する内容でお願い致します。
経営事項審査とは
経営事項審査とは、公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受ける必要がある審査のことです。
企業の施工能力や財務状況、技術力などを客観的に評価して、その結果を数値化するもので、公共工事の入札に参加するために不可欠なプロセスとなっています。
具体的には、「経営規模等評価」と「総合評定値(P点)」の算出が外部機関で行われて、公共工事を請け負うためのいわゆる「通知表」のような役割を果たしています。

経営事項審査の要件
経営事項審査を受けるには、次の2つの要件を満たす必要があります。
建設業の許可
ともかく、経営事項審査を受けるには建設業の許可を受けていることが必須です。経営事項審査を受けるには、国や都道府県から建設工事を行うための正式な建設業許可を得ていなければなりません。
経営状況分析
経営状況分析とは、会社の財務状況を客観的に分析することです。具体的には、自己資本額や利益額、キャッシュフローなど、経営の健全性を示す指標を専門機関に提出して分析してもらいます。この分析結果は、経営事項審査の評価項目の一つとなります。
経営事項審査の事業承継とは
経営事項審査の事業承継とは、建設業を営む企業が、事業を後継者や他社に引き継ぐ場合に、現行の経営事項審査の評価を承継することです。
M&Aや事業譲渡を行うと、新しい法人が事業を引き継ぐため、改めて、一から経営事項審査を受ける必要がありますが、事業承継の特例を利用することで、引き継ぐ側の経営事項審査の評価を一定期間、承継することができます。これで、承継後の入札機会を確保しやすくなり、事業の継続性を高めることができます。この制度は、特に中小企業のスムーズな事業承継を支援する目的で設けられています。
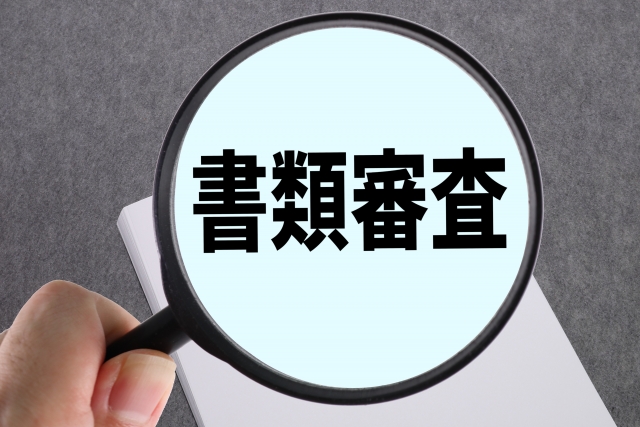
静岡県の経営事項審査事業継承の要件
下記の要件を満たす場合は、完成工事高、利益額、営業年数を引継ぐことができます。事業継承日、または法人設立日を審査基準日として申請します。
事業継承
当期事業年度開始日から遡って2年以内、または3年以内に許可のある個人に限る建設業者(被承継人)から建設業の主たる部分を承継した者(承継人)がその配偶者、または2親等以内の者であって、次のいずれにも該当する場合は承継することができます。
・被承継人が建設業を廃業すること
・被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること
・承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること
法人成
当期事業年度開始日から遡って2年以内、または3年以内に許可のある個人に限る建設業者(被承継人)から建設業の主たる部分を法人に限る承継した者(承継法人)であって、次のいずれにも該当する場合は承継することができます。
・被承継人が建設業を廃業すること
・被承継人が50%以上出資して設立した法人であること
・被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること
・承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること
経営事項審査の事業承継の手続き
経営事項審査の事業承継の手続きは、状況によって複雑になりますが、基本的な流れは以下の通りです。
事業譲渡契約・吸収合併契約
まず、事業を譲渡する側と承継する側で、事業譲渡契約、または吸収合併契約を締結します。この契約には、承継する事業の内容、資産、負債などが明確に記載されている必要があります。
承継後の建設業許可の取得
事業を承継する側の法人が、建設業許可を新たに取得するか、または既存の許可を承継する手続きを行います。
M&Aや事業譲渡の場合、新しい許可の取得が必要となるのが一般的です。
事業承継の特例申請
建設業許可を取得した後、各地域の地方整備局や都道府県の建設課など、許可行政庁に対して事業承継の特例申請を行います。
この申請では、事業譲渡契約書や承継する事業の概要、経営事項審査の評価を承継する旨を記載した書類などを提出します。
経営事項審査の申請
承継後の法人名で、承継前の法人の有効な経営事項審査の結果を基に、改めて経営事項審査を申請します。これにより、承継前のP点を引き継いだ形で審査を受けることができて、事業継続が可能になります。
Q&A
まとめを兼ねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。



